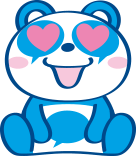「裸電球」がまぶしかった!昭和の家族団らんを照らし続けた暖かな白熱電球

日本の代表的なフォークバンド・かぐや姫に『赤ちょうちん』という歌がある。1974年(昭和49年)に発表された。小さな部屋に暮らす若い男女の暮らしを描いたものだが、こんな歌詞で始まるのだ。
「あのころふたりのアパートは 裸電球まぶしくて」
昭和の時代、家の中を照らす明かりは「裸電球」すなわち「白熱電球」だった。そして、それは“まぶしかった”のである。
エジソンによる白熱電球
白熱電球は、19世紀に米国の発明家トーマス・エジソンによって、実用化された。電球の中にある線、すなわちフィラメントに電気を流して光る仕組みである。日本でも明治時代に入って、各家庭に電気が普及していく中で、この白熱電球は大きな存在となっていった。当時は「1灯いくら」という契約だったので、ひとつの電球が契約の単位だった。そのため、家で最も家族が集まる居間に、唯一の電球がセットされることが多く、天井からぶら下げられた電球の下に食卓が置かれた。団らんを演出する、暖かく柔らかい色だった。
家の中を照らす明かり

こうした電灯には、いわゆる“傘”はあるものの、卵型の白熱電球がそのままセットされることも多く、それが「裸電球」と呼ばれるゆえんでもある。裸電球には、黒い色のソケットがある。その横にスイッチがあり、それをひねって、電灯を点けたり消したりした。そこから長い紐を食卓近くまで伸ばして、それを引っ張って操作していた家庭もあった。一人暮らしのアパートの部屋にも「裸電球」があった時代である。暗い中、ソケットのスイッチで明かりを点ける時、「ただいま」とひとりごちた人も多いのではないだろうか。
縁日の夜店でも活躍
家庭だけではない。神社の境内などの縁日に並ぶ夜店でも、白熱電球は欠かせない。ひとつひとつの店に、裸電球の白熱灯があった。金魚すくい、風船釣り、綿菓子やイカせんべいなど、こうした夜店の魅力を演出するのは、蛍光灯では出せない、何とも人肌になじむ、黄色く暖かい白熱電球だった。縁日の夜店というと、やはり裸電球であろう。
電球交換の思い出

白熱電球は、使っている内に突然切れる。中のフィラメントが次第に細くなっていき、切れると寿命なのだが、電球交換の時には注意が必要だった。切れたからといって、すぐに電球に触ると、その熱さで火傷してしまう。また、電源を切ってから交換しないと、指先にビリビリきてしまうこともあった。外した電球を耳元で振ってみると「シャリシャリ」と、切れたフィラメントの欠片が中で音を立てた。その電球が「使えない」ことを再確認する、何やら電球交換の“儀式”のようだった。
時代の波と共に・・・
蛍光灯が登場し、白熱電球と共に使われるようになった。明るさが際立っていた上、突然切れることもなかった。長く白熱電球を作り続けてきた大手メーカーも、2010年(平成22年)に製造を終えて、白熱電球120年の歴史に幕を下ろした。現在は、蛍光灯から、さらに寿命の長いLEDへと、照明器具は変遷している。
過ぎ去りし昭和の時代、家庭の団らんに明かりを灯し続けたのは、白熱電球だった。一人暮らしのアパートの部屋で励ましてくれたのも「裸電球」だった。その暖かい色は、そんな思い出を、今も懐かしく、そしてまぶしく、照らし続けてくれているようだ。
【東西南北論説風(480) by CBCテレビ特別解説委員・北辻利寿】
※『北辻利寿のニッポン記憶遺産』
昭和、平成、令和と時代が移りゆく中で、姿を消したもの、数が少なくなったもの、形を変えたもの、でも、心に留めておきたいものを、独自の視点で「ニッポン記憶遺産」として紹介するコラムです。
CBCラジオ『多田しげおの気分爽快!!~朝からP・O・N』内のコーナー(毎週水曜日)でもご紹介しています。