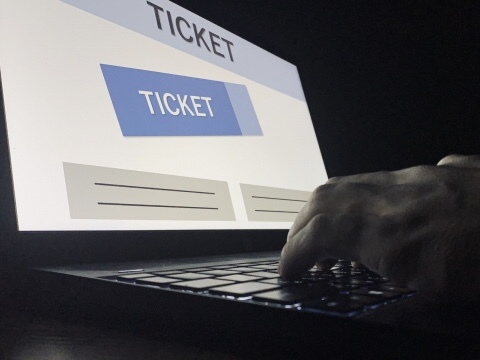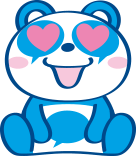ウクライナで23%のエリアで埋まったまま。最悪の兵器「地雷」

22日から東京でウクライナ地雷対策会議が開催されています。ウクライナ国内には、ロシアが設置した大量の地雷があるとされ、この会議ではその処理や今後の復興などを話し合っています。そこで、この日に放送された『CBCラジオ #プラス!』では、CBC論説室の石塚元章特別解説委員があらためて地雷の怖さや、撤去に立ちはだかる課題について解説しました。聞き手は永岡歩アナウンサーと三浦優奈です。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴く地雷とはどんな兵器?
あらためて地雷とはどんな兵器なのかについて、おさらいしましょう。
地面に置いたり、少し地中に埋めたりして、そこに兵士や戦車などが接近してきたら感知して爆破させるという兵器。
2022年の2月にロシア侵攻が開始されてから、ウクライナではあちこちの場所に地雷が埋められたのですが、後に撤退した一部の場所では地雷がまだ残っています。
国連開発会議の調査によれば、ウクライナの国土で実に23%ほどのエリアで地雷や不発弾があってもおかしくないと言われています。
ウクライナ地雷対策会議は今回3回目で、復興に必要な地雷の除去方法について話し合っているのです。
地雷の特徴
兵器はどれも人間にとってひどいものではありますが、特に地雷はひどい兵器であるという特徴を3つ持っています。
鉄砲や銃といった通常の兵器なら直接的に狙った相手が攻撃対象となりますが、地雷には無差別攻撃という特徴があります。
誰がそこを通るかわからないため、いったん設置すると誰もが亡くなってしまう可能性があります。「悪魔の兵器」と呼ばれる所以です。
ある調査では地雷の被害者の7割が戦争とは関係のない人々であるとされています。
もう1つの地雷の特徴は安価であること。
そこまで高度な技術がなくても爆薬があれば作れてしまい、数百円程度で似たようなものが作れてしまいます。
たくさん置くこともできることから、あたかも平原や草原のように「地雷原」という言葉があるぐらいです。
戦争が終わっても残り続ける
そして3つ目の特徴は、一度仕掛けてしまうと、いつまでもそこに残り続けるということ。
戦争が終わっても自動的に爆発機能が解除されるわけではありません。
また、仕掛けた側もどこに何個仕掛けたか記録していないことがあったり、もしわかっている人がいてもすでに戦場から去っていて、現状が不明なことも多くあります。
そのため、戦後復興で開発しようと思っても、民間の一般人からするとどうやって探せば良いのかわかりません。
金属探知機などで探す方法もありますが、安い地雷だと木やプラスチックで作っているケースもあり、探すのも意外と容易ではないそうです。
対人地雷を禁止しようという動きはあるが…
人間にとって大変危険な地雷の使用を禁止するための条約、対人地雷禁止条約が1997年(平成7年)にカナダで締結されました。
日本はもちろん160か国とかなり多くの国が参加しているのですが、アメリカやロシア、イスラエル、中国など、地雷を利用しそうな国が参加していないというのが残念な点。
ウクライナは参加しているため、ロシアが一方的に地雷を使っているという状況。
これが不平等だということで、ウクライナは脱退を表明しています。
まだ戦争がなかなか終わらないのですが、それだけに日本で開かれるウクライナ地雷対策会議は重要度を増してきています。
(岡本)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。