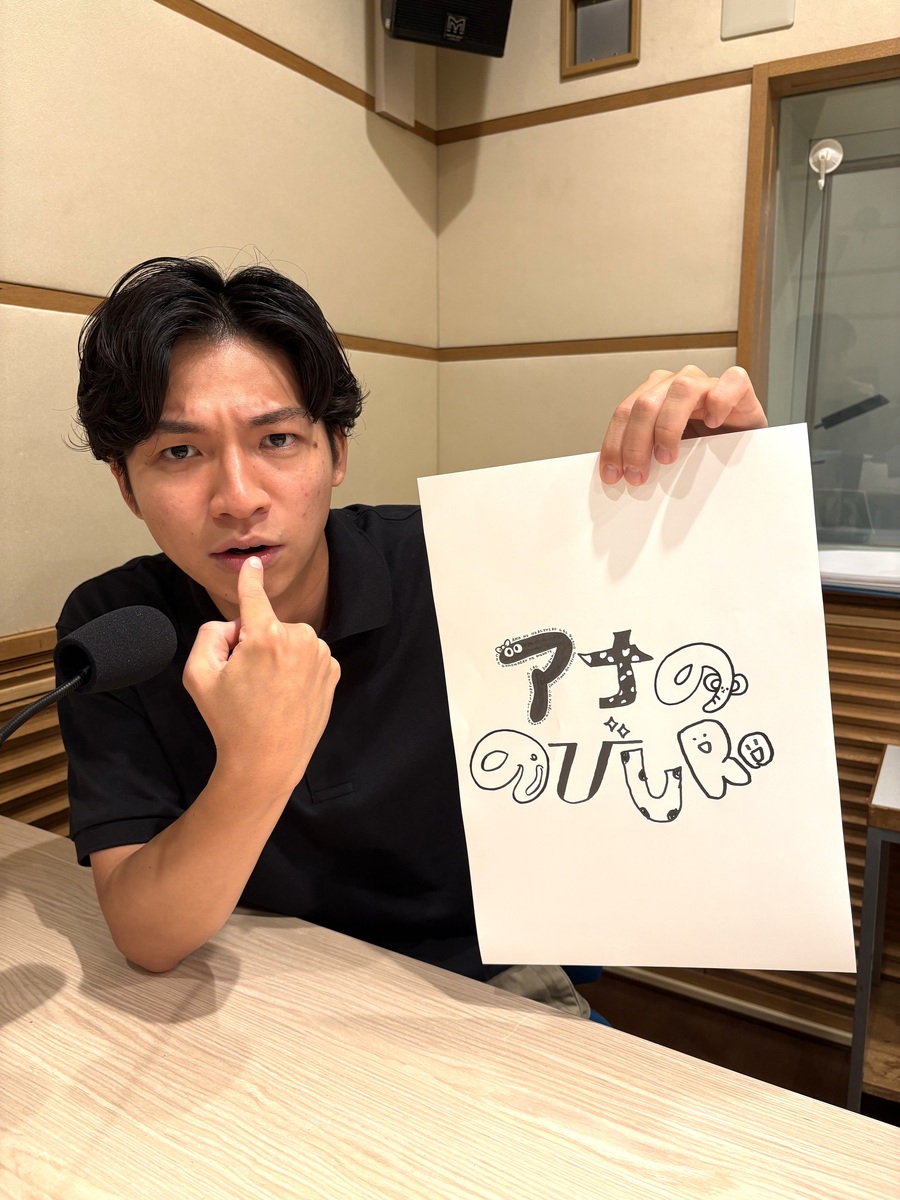CBC松本道弥アナが潜入!うなぎの常識覆す「メスだけ養鰻場」の秘密

次世代の人気アナを目指す若手アナウンサーたちがしのぎを削る、のびのびトーク番組CBCラジオ『アナののびしろ』。7月26日の放送では、松本道弥アナウンサーが、愛知県高浜市の養鰻場で体験した驚きの取材内容を披露しました。私たちが普段食べているうなぎの9割がオスという事実から、最新技術で作られる「メスうなぎ」の秘密まで、知られざるうなぎの世界について熱く語りました。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴くそもそも「土用の丑の日」とは
連日の猛暑が続く中、暑い日に精をつける日本人の定番といえばやはり「うなぎ」ではないかと話を切り出した松本。うなぎを食べる習慣がある「土用の丑の日」について解説を始めました。
「土用」とは立春・立夏・立秋・立冬の直前のおよそ18日間を指す言葉で、年に4回あります。特に暑さで体調を崩しやすい「夏の土用」は昔から重要視されてきました。
「丑の日」は365日を十二支に割り当てた時に丑にあたる日。土用の期間中の丑の日に該当する日が「土用の丑の日」となり、年によっては2回巡ってくることもあります。
なぜ土用の丑の日にうなぎを食べるのか。松本は恵方巻の例を挙げながら、海苔業者のキャンペーンのようなマーケティングの賢さを感じると語ります。
うなぎについては平賀源内が広めたという説を紹介。本来の旬は冬のうなぎを、売れ行きが落ちる夏に売るため、「本日土用丑の日」と貼り紙をしたところ客が殺到したのが始まりだったそうです。
うなぎの9割はオス
話題は、松本が取材で知った「面白いうなぎ」の話へ移ります。
「皆さん、うなぎを食べる時にうなぎさんの性別って気にしたことありますか。実は私たちが普段食べているうなぎというのは、9割ほどがオスなんですよ。9割がオス、1割がメス。メスが非常に少なくてレアなんです」
さらに驚きなのは、うなぎは成長過程で性別が変わるということ。稚魚の段階では性別が決まっておらず、成長する過程で性別が分かれるというのです。
通常、私たちの手元に届くうなぎの9割がオス。しかし、松本が取材に訪れた愛知県高浜市の「ヤマヤ養魚」では、最新技術により9割以上がメスになるという画期的な育て方を実践していました。
大豆イソフラボンでメスうなぎ誕生?
その方法は、「餌に大豆イソフラボンを混ぜる」というものです。大豆イソフラボンは女性ホルモンと似た構造の成分で、餌20キロに対してわずか80グラム混ぜるだけで効果があるそうです。
その理由は「よくわかっていない」とのこと。ただ、こういった研究が進んでいて、実際に検査すると9割以上がメスになることが確認されているそうです。
メスうなぎはオスより大きく、300グラム以上で身も太い。さっぱりとしていて、白身魚のような淡白な味わいだといいます。
メスうなぎが好きな人は「メスうなぎばかり食べる」ほど人気があるそうです。
養鰻場での出荷作業体験
ヤマヤ養魚で、うなぎの出荷作業を体験した松本。大きなビニールハウスの扉を開けると、そこには大きな池が広がっていました。その中に4つの養鰻池があり、1つの池で約4万匹のうなぎを育てているそうです。
出荷時は養鰻池にホースとポンプを取付け、うなぎを水ごと別の池に運びます。松本が体験したのは胴万(どうまん)という籠に、うなぎを詰める作業です。胴万ひとつに35キロのうなぎが入るため、その重さはかなりのもの。持ち上げるのも、水の中での作業も重労働でした。
しかも屋根はあってもクーラーはなく、汗をかく大変な力仕事だったようです。
「うなぎを食べるとき、養鰻業者の皆さんの苦労があって、おいしいうなぎが私たちの口に届いているんだなと改めて実感しました」
最後に松本は、7月31日の今年2回目の土用の丑の日に向けてリスナーに呼びかけました。
「この大変な出荷作業を通過したうなぎなんだぞと、感謝の気持ちを持って食べてみてください。そしてうなぎの性別、オスかな、メスかな、よければ気にしてみてください」
(minto)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。