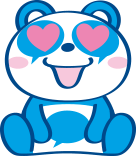伝統の高岡銅器で涼を届ける!新高岡駅に響く風鈴の調べ

富山県の北陸新幹線・新高岡駅南北通路には、高岡銅器で作られた風鈴が45個飾られ、涼しげな音色が訪れる人々を迎えています。7月21日放送の『CBCラジオ #プラス!』では、高岡銅器協同組合理事長の宮津健志さんに、この取り組みと高岡銅器協同組合の活動について詳しく伺いました。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴く駅に響く涼やかな調べ
この展示では、地元の高岡第一幼稚園の園児たちが願い事を書いた短冊も一緒に飾られています。
実際に風鈴の音色が流れ、光山雄一朗アナウンサーと三浦優奈は「気温が体感で下がる感じ」「風鈴の音に耳を澄ますのは最近なかった。こういう時間も大事」と、その涼やかな音に聞き入りました。
この取り組みは「高岡に来られたお客様に、少しでも風鈴の音を感じていただけるように」という思いで1993年(平成5年)から続いています。
2015年の北陸新幹線開業後は、新高岡駅に場所を移して引き続き行なわれているそうです。
400年続く伝統の始まり
高岡銅器の歴史は古く、江戸時代初期の1611年(慶長16年)にさかのぼります。加賀藩2代藩主の前田利長が高岡の城下町を発展させるため、河内(大阪)から7人の鋳物師を招いて鋳物作りを始めたのが起源です。
当初は鉄製の鍋や釜などの日用品が中心でしたが、技術の発達とともに仏具や美術工芸品の制作へと広がっていきました。
明治以降は、精緻な鋳造・彫金の技術が国際的にも高い評価を受け、パリやフィラデルフィアの万国博覧会での受賞歴もあります。
高岡銅器協同組合の活動
高岡銅器協同組合は、茶道具や花器、仏具などの卸売を行なう企業40社で構成されています。
製造関連企業の経営・生産支援、後継者育成、技術継承、産学共同開発、市場拡大などを通じて高岡銅器のPRと販売支援を行なっていて、風鈴の展示はこれらの事業の一環とのこと。
駅を訪れた人が風鈴の音色を聞いて足を止める様子を見ると、宮津さんは「よかった、気づいてくれた」と嬉しくなるそうです。
高岡銅器協同組合の年間を通じた活動として、5月には東京・日本橋とやま館で100万円以上の商品を集めた「至高の逸品展」を開催。これは“購買可能な美術館”として、お客さんから高い評価を得ています。
7月は風鈴展示。8月は市内の銅像清掃。11月には同じく日本橋とやま館にて、価格を抑えた各社のイチオシ品や新商品、珍品を200点展示する「高岡銅器楽園市」を開催するなど、高岡銅器の知名度向上と普及に努めているとのことです。
鋳造の町・高岡の魅力
風鈴の制作は毎年行なうのではなく、4年に一度くらいのペースで新しく作っているそうです。
CBC論説室の石塚元章特別解説委員は「加工しやすく光沢が綺麗など、銅ならではの特徴がある。高岡の銅器も見た目や銅像など、いい製品がいっぱいある」とコメント。
宮津さんも「高岡は、銅器だけでなく錫、鉄、金、銀なども作る金属の町です。お越しいただければ、いろいろ楽しんでいただけるのではないか」と、町全体の魅力をアピールしました。
新高岡駅の風鈴展示は8月28日まで。猛暑の中、400年以上の歴史を持つ高岡銅器の涼やかな音色が、訪れる人々に一時の涼を届けています。
(minto)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。