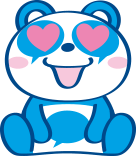あなたは知ってる?芥川賞・直木賞以外にも本の作品賞が多数

7月16日、第173回芥川賞・直木賞の選考会が東京で行なわれましたが、両方とも該当作なしとなりました。これは27年半ぶりのことで6回目とのことです。この日に放送された『CBCラジオ #プラス!』では、芥川賞・直木賞にちなんで、さまざまな文学賞のトリビアや出版不況の現状などを紹介。そこから見える日本人の読書について、CBC論説室の石塚元章特別解説委員が解説しました。聞き手は永岡歩アナウンサーと三浦優奈です。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴く芥川賞と直木賞の違い
芥川賞と直木賞は日本の文学で有名な賞としてよく並べて紹介されますが、その特色は異なります。
芥川賞は主に文芸雑誌に掲載される純文学が対象で新人が賞を獲る傾向にあります。
一方で直木賞はエンタメ系の作品が多く、すでに文庫化されているケースも多く、すでに人気作家だったり中堅作家が取る傾向にありました。
ただ、最近は両賞の境目がなくなってきているという指摘もあります。
この2つの賞はもともと1935年(昭和10年)に、劇作家で文藝春秋社を創った菊池寛が創設。
毎年1月と7月に発表されますが、なぜこの時期かというと、2月と8月は「ニッパチ」といって物が売れないと言われています。その時期に合わせて、本の売り上げを上げるためという説があります。
直木賞の「直木」って誰?
賞の名前の由来ですが、芥川賞はもちろん芥川龍之介ですが、一方で意外と出てこないのが直木賞。
直木三十五という作家で、当時、新聞小説などで人気を博していました。これはペンネームで、名字は本名の植村の「植」の字をバラして「直木」ですが、下の名前は年齢を元にしたもの。
31歳の時に直木三十一を名乗り、毎年ひとつずつ増やしていましたが、35歳の時に菊池寛から「いい加減にしろ」と注意をされて、それ以降はそのまま三十五の名前を使い続けたそうです。
さまざまな賞が濫立
そして、日本では今や芥川賞や直木賞以外にもさまざまな賞があります。
作家の名前がついた賞でいえば、三島由紀夫賞や谷崎潤一郎賞、江戸川乱歩賞に川端康成文学賞など。
その他最近かなり有名になってきたのが本屋大賞。
これは全国の書店員さんが選ぶ賞で、よく本屋さんのポップに書かれていたりもします。
三浦が挙げたのは「どくミス!」で、これは2013年から開催されている「読者が選ぶ翻訳ミステリー大賞」の略です。
似た名前では「このミス」という、『このミステリーがすごい!』大賞というのもありますし、自治体が選出する賞などもあります。
賞を獲った本が売れるということもあってか、今やさまざまな賞が濫立しています。
一方では売れる本がノミネートされるという話もあり、これはどちらが先かわからない場合もありますね。
読書離れは本当か
ただ、これだけ本が売れる売れると言われていても、何年か前から「出版不況」、「読書離れ」という話題が出てきており、実際に数字に表れてきています。
10年前と比べて書店数は全国で4千ほど減り、本屋が1軒もない市区町村が493。
文化庁の国語世論調査によれば、16歳以上で1か月に1冊も本を読まない人が6割という結果もあります。
さらに雑誌の売れ行きも減ってきており、ピーク時だった1996年に1兆5千600億円だった売り上げが、今や4千億円ほどと激減。
雑誌は完全にネットに取って代わったといえます。
一方で電子書籍の売り上げは伸びていることや、小中学生の読書量が増えているというデータもあり、読書離れとは言い切れないのかもしれません。
もし今、「最近、全然本を読んでいないな」と思った方は、さまざまな賞をチェックしてみて、まずはそこから手にとってみても良いかもしれません。
(岡本)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。