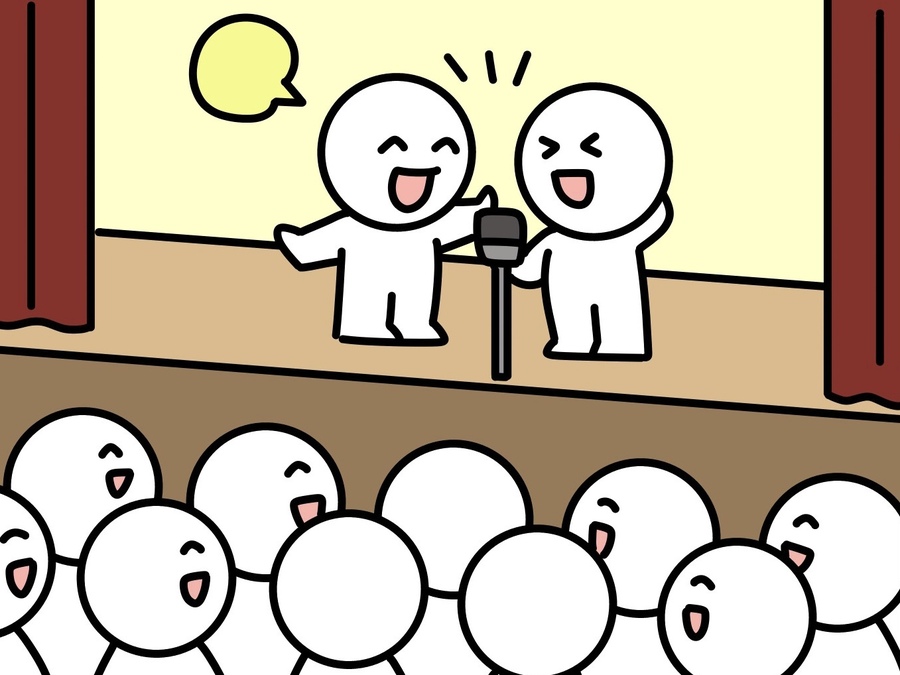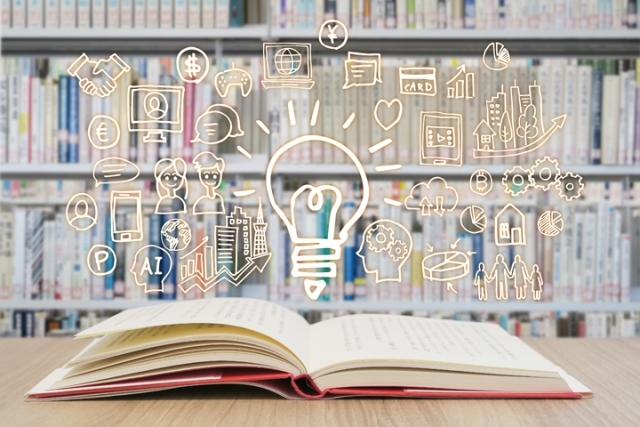高市総理初で注目の「党首討論」。25年経って課題が見えてきた

日本の国会で11月26日午後、高市早苗総理にとっては初めての党首討論が行なわれ、日中関係や年収の壁などを題材にした議論が注目されました。この「党首討論」は、国会の議論を活性化する目的で2000年から始まったものです。26日朝に放送された『CBCラジオ #プラス!』では、党首討論の課題について、CBC論説室の石塚元章特別解説委員が解説しました。聞き手は永岡歩アナウンサーと三浦優奈です。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴く討論の時間は45分
党首討論は各党の党首どうしが1対1で論戦を戦わせるもので、分数は45分と決まっています。
それぞれの党の時間は議席数で割り振られ、立憲民主党の野田佳彦代表は28分と最も多く、国民民主党の玉木雄一郎代表は8分、公明党の斉藤鉄夫代表は6分、参政党の神谷宗弊代表は3分となっています。
衆議院か参議院で10人以上議員のいる政党しか参加できないため、この4党以外は参加できません。
石塚が今回の党首討論のポイントとして挙げたのは、初めてとなる高市総理がどのような討論をするのかという点、これまで与党だった公明党が野党に回るという点、そして参政党が初めて参加するという点の3つ。
45分が短いのではないかとの意見もあります。例えば参政党の場合は与党側の回答も含めて3分しかありません。
党首討論が始まって25年
党首討論が生まれたのは、国会を改革し議論を活性化しようという目的で1999年にできた国会審議活性化法という法律によるもの。
2000年に衆議院と参議院に国家基本政策委員会ができ、ここで党首討論を行なうことになりました。
党首討論の正式な名称は「国家基本政策委員会合同審査会」というものです。
モデルとなったのはイギリスの下院で行なわれているクエスチョン・タイムと言われますが、日本の党首討論では違う点がいくつかあります。
イギリスでは国会期間中、月曜から木曜まで毎日行っている上に、水曜日は首相が行いますが、その他の日は大臣が対象。
野党も党首だけではなく議員が聞いても良いことになっていて、さらに与党内で質問をしても良いことになっています。
党首討論の課題
実は日本でも当初はイギリスのように毎週水曜に行うようにしていたのが、だんだん回数が減っていくことに。
2000年は8回といきなり少ないスタートとなっていますが、2001年は7回、さらに開催ゼロの年もありました。
有名なのは2012年の民主党政権の時、当時の野田総理と安倍晋三自民党総裁との党首討論。野田総理が「議員定数削減に応じるなら解散しても良い」と発言したところ、安倍総裁が「本当ですね?解散しますね」と言質を取り、結果、民主党は下野することになってしまいました。
また、2018年の党首討論では安倍総理(当時)が45分中6割ぐらい発言していたということで、野党が十分に質問できなかったとの批判が起きました。
モデルとなったイギリスは二大政党制ですので野党にも十分時間がありますが、野党が他党化してしまった現在の日本では不向きとなってしまったようです。
また、野党側も党首討論よりもテレビ中継が入って時間の長い予算委員会の方がアピールできるとの思惑もあり、そちらの方に力が入っているのかもしれません。
そして、そもそもディベートの文化が日本には馴染まないという声もあります。
さまざまな課題がありますが、せっかく行われる党首討論ですので、有効な議論を期待したいところです。
(岡本)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。