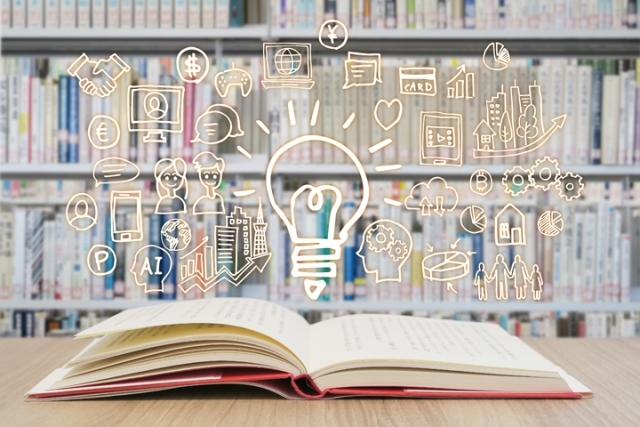五輪とデフリンピックで強い国が違うのはなぜ?

11月26日まで日本で開催中の「東京2025デフリンピック」。競技結果の勢力図がオリンピックとは大きく異なっています。11月25日放送の『CBCラジオ #プラス!』では、光山雄一朗アナウンサーと山本衿奈が、朝日新聞の記事をもとに、デフリンピックの背景などについて取り上げました。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴くデフリンピックの強豪とは
デフリンピックは聴覚障害者の国際大会で、競技ルールはオリンピックとほぼ同じですが、競技結果の勢力図が大きく異なります。
特に陸上男子100メートルでは、オリンピックならアフリカ勢やジャマイカ勢が上位を独占するイメージがありますが、デフリンピックでは全く異なり、ヨーロッパ勢や日本が上位に並びます。
光山「スタートの合図がランプになる以外はほぼ同じルールなのに、これほど違うのは興味深い」
一体なぜ競技力に違いがあるのでしょうか?
競技力に差ができる理由
競技力の違いの理由に、歴史と教育環境があります。
デフリンピックは1924年にフランスで始まった歴史を持ち、ヨーロッパを中心に発展した経緯があります。
こうした歴史的土壌が、現在の競技力にも影響を与えているといいます。
さらに、選手を発掘し育てる「組織の体制」が重要ですが、中南米やアフリカでは聴覚障害者スポーツの団体が十分に機能していないケースも多いそうです。
一方で、日本やヨーロッパには聾学校が古くからあり、デフスポーツが広まりやすい環境が整ってきました。
教育環境や支える組織の充実度が、競技力や選手層の厚さに直結しているようです。
世界各地での開催が必要?
地域差を減らすには、デフリンピックの開催地を世界各地に広げることが重要です。
大会を通して聴覚障害者への理解が高まり、社会の意識が変わるきっかけになるためです。
山本自身も、日本での開催によって関心が高まったそう。
アフリカや中南米で開催されれば、その地域でも理解が進むはず。
開催地の多様化に期待を寄せました。
日常の出会いが理解のきっかけに
光山は、日常生活の中で感じた聴覚障害者との関わりについて語りました。
光山の妻が訪れたカフェで、聴覚障害の店員が指差しやメモを使って丁寧に接客してくれたことがあり、その笑顔に「また行きたい」と強く感じたといいます。
光山「誰もが働きやすい職場の環境作りっていうのは、根付いてきたり、増えてきたりしているんだなって」
スポーツの世界でも、視覚障害者への理解を深め、輪が広がることに期待しました。
山本も、聴覚障害の方と接する機会があると話し、簡単な手話でも相手が喜んでくれることを経験したとのこと。
「ありがとう」の手話を実演しながら、「もっと積極的に手話を覚えたいと思える」と語りました。
こうした日常での小さな交流が障害への理解を深める大切な一歩です。
その一歩が、いずれ大きな輪になるのかもしれません。
(ランチョンマット先輩)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。