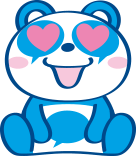管理しきれない「“負”動産の処分」の強い味方!「相続土地国庫帰属制度」とは?

昨今、少子高齢化により中小企業や小規模事業者の後継者難が大きな経営課題の一つとなっています。「人生100年時代」と言われているこの時代だからこそ、元気なうちに資産の管理や、のスムーズな承継について考えていく必要性が高まっているのです。CBCラジオ『北野誠のズバリ』「シサンのシュウカツにズバリ」では、事業承継と資産承継について専門家をゲストに学んでいきます。7月16日の放送では、「“負”動産の処分」について北野誠と松岡亜矢子が三井住友トラストグループ 三井住友信託銀行株式会社星ヶ丘支店 塩崎淳さんに伺いました。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴く管理できない土地はどうしたらいい?
今回は、2024年4月から相続登記は義務化されたことに関連し、不動産の「不」を「勝つ、負ける」の「負ける」と書いて「“負”動産の処分」について、取り上げました。どのような内容でしょう?
塩崎「最近、『親の実家が空き家になって困っている』『相続したけど管理が大変な不動産を手放せる方法はないのか?』といったご相談も増えています」
市街地の不動産なら価値がありますが、田畑や山林は相続しても実質的な管理が大変です。
北野「欲しくない不動産だけを相続せず、放棄できますか?」
塩崎「残念ながらそれはできません」
相続放棄する場合、相続財産の中に価値がない(相続したくない)財産が含まれていても、一部のみを放棄することはできないと塩崎さんは言います。
相続放棄とは、プラスの財産・マイナスの財産全てを放棄することです。その場合は相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があると続けます。
北野「売れればいいけど、固定資産税も払ったり、草取りに行ったり正直しんどいですよね」
では、いらない不動産だけを手放す方法はあるのでしょうか?
塩崎「あります!それが相続土地国庫帰属制度です」
北野「漢字が多くて噛みそうですね(笑)。どんな制度なんですか?」
塩崎「相続したけど、誰もいらない土地ってありますよね?それをお金を払って国に引き取ってもらう制度」
例えば、祖父の土地を父が相続、さらに相続で自分に引き継がれた、そのような土地を手放せる制度なのです。
メリットとデメリットは?
メリットは全部の財産を放棄する事なく相続した上で、不要な土地を国に引き取ってもらえること。
国が国有地として管理してくれる安心感も。デメリットは費用が掛かる、複雑な条件があると説明する塩崎さん。
北野「費用はどれくらいかかりますか?」
塩崎「申請時に審査手数料として1筆あたり14,000円。負担金は、土地の管理負担を免れる程度に応じてかかります」
宅地なら通常は面積に限らず20万円ですが、例えば市街化区域といった市街地を形成している区域の宅地なら100㎡あたり約55万円程度に。また森林は必ず面積に応じて算定することとなり、1,500㎡で約27万円程度になると塩崎さん。
塩崎「承認されなかった場合や申請を取り下げた場合でも、審査手数料は戻って来ない点は注意が必要」
却下・承認されないケースに注意
申請方法は次の通り。
1、 相続で土地を取得した人が法務局(法務大臣)に承認申請
2、 法務局(法務大臣)は審査と実地調査
審査で却下、実地調査で却下・承認されないケースもあります。審査で承認されれば、負担金を納付し晴れて国、国庫に帰属される流れです。
法務省は標準処理期間を8ヶ月としていますが、事案によってはそれを超えることもあります。
塩崎「承認申請書を作成する際に、地図等にその範囲をマーキング。近くからと、遠くから、国(法務局)がわかるよう境界点の写真などを添付したり、境界に杭を打つ事も必要」
申請は、建物がなく所有権に争いがないことが前提。国が通常の管理または処分を阻害する工作物などがある土地、抵当権などが設定されている土地、通路に該当する土地、土壌が汚染されている土地、境界が不明な土地などは、申請しても却下されたり認められない可能性が高くなります。
北野「実際、この制度でどれくらい国に引き取ってもらってるんですか?」
5月29日付の日本経済新聞(電子版)には、「国が引き取った件数は、2024年度1200件を超え、23年度の5倍弱に増えた」との報道も。
法務省が2025年6月に発表したデータでは、帰属件数1,699件。内訳は宅地634件、農地531件、森林105件、その他429件(雑種地や原野等)となっています。
塩崎「関心がある方はまずお近くの法務局に相談する事も可能です。登記事項証明書や固定資産税納税通知書、土地の現況や全体がわかる写真とかを持っていくと良いでしょう」
北野「条件はたくさんありますけど、利用者は増えているんですね。宅地や農地だけでなく山林も承認されているんですね」
相続した不動産をどうするか、悩んでいる方はまず法務局や専門家に相談して、自分の土地にどんな選択肢があるのか考えてみてほしいと呼びかけました。
(葉月智世)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。