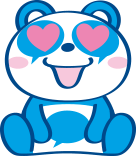台湾有事への備えは?沖縄離島からの住民避難計画への不安と課題

生まれて初めて訪れた沖縄の地は石垣島だった。美しい海と空はもちろん、沖縄が持つ“空気感”に魅かれて、沖縄本島、さらに数々の離島にも通うようになった。気がつくとその数は60回近くになる。そんな経験からいろいろ考えても“この計画”がなかなか腑に落ちない。「台湾有事」を想定しての、政府による住民らの避難計画である。戦後80年を迎える中、沖縄への思いが強くなる。
島民ら12万人の避難計画
政府は、中国が台湾に対し武力行使をする事態を想定して、沖縄県の先島諸島から住民と観光客を避難させる計画を、2025年(令和7年)3月末に公表した。「台湾有事」が日本にも影響する事態になり、政府が「武力攻撃予測」を宣言した場合に人々を守るための計画である。避難の対象となるのは、宮古島市、石垣市、竹富町、与那国町、そして多良間村の5つの市町村の住民11万人、そして、それぞれの島を訪れている観光客1万人、合わせて12万人となる。
船舶などで九州へ移動
具体的には、自衛隊や海上保安庁の船舶、そして民間のフェリーや航空機などを使う。1日に2万人を運び、6日間で避難を完了する。避難した人の内、島民11万人を分散して受け入れるのが、九州や山口県などの8県である。避難する側と避難先の組み合わせは決められていて、5万5,000人と最も多い宮古島市から避難した人たちは福岡県など、4万9,000人の石垣市からの避難は山口県などが受け入れることになる。避難の期間は1か月程度と想定されている。もちろん、あくまでもシミュレーションである。
非現実的?想定への不安

しかし、この計画をさらに噛みしめてみると、数々の不安が湧いてくる。まず「6日間」という避難にかける時間である。「有事」ということは、最悪は紛争が始まっているのである。以前に与那国島を訪れた時に、好天に恵まれて海の向こうに台湾の島影を見ることができたが、与那国島と台湾の距離は、わずか100キロほどと近い。「6日間」という悠長な時間はあるのだろうか。また、移動に使う交通手段は、急きょ用意できるのか。さらに、避難先の受け入れ態勢にも心配がある。九州などのホテルや旅館が宿泊先になるのだが、「すべて空室」という想定である。当然、平時はそれぞれに旅行やビジネスの客がいるだろう。その人たちにすみやかに部屋を空けてもらうことは可能だろうか。そして、受け入れる自治体の負担をどの程度に想定しているのか。
避難する側への配慮は?
最も気になるのは、島の人たちの心である。筆者が沖縄を好きな理由のひとつに、生まれ育った琉球の地を愛する人たちが多いことがある。誰しも故郷への思いはあるが、沖縄の人たちは特にそれが強いと感じている。そんな人たち、とりわけ「おじい」「おばあ」と親しまれる年配の人たちが、すんなりと計画通りの避難に応じてくれるだろうか。また、病気や体を傷めているなども当然少なくないはず。避難する側への配慮は欠かせない。
平成と令和の防人たち

政府がここまでの計画を公表するほどに、台湾など東アジアを取り巻く状況は、予断を許さないと見られている。2016年(平成28年)に与那国島に陸上自衛隊の駐屯地が開設されたことを初めとして、2018年(平成30年)には宮古島、2023年(令和5年)には石垣島と、離島の自衛隊駐屯地は増えている。多くの自衛隊員が島に移り住んでいる。ノンフィクション作家の沢木耕太郎さんが、かつて若き自衛隊員について書いた文章に「防人のブルース」というタイトルをつけたが、まさに“平成と令和の防人(さきもり)”と言えよう。すべては緊張状態ゆえのことである。
今回公表されたのは初期計画であり、政府は2026年度中に避難訓練を行うなど、さらに具体化を進めるという。計画を“机上の空論”にさせないためには、避難する側と受け入れる側、双方が納得する細やかな説明が必要である。そして何より、こうした避難が必要ないような日本ならではの外交努力、政府にはまずそれが求められるだろう。
【東西南北論説風(580) by CBCマガジン専属ライター・北辻利寿】