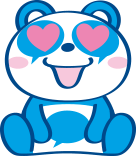一見バラバラだけど…ヘルメットの色やラインに隠された意味

現場作業をする上で安全を守るために欠かせないヘルメットですが、よく見ると色やデザインがまちまちなことにお気づきでしょうか?白や黄色、青色や赤色などカラーも数種類あれば、そこに装飾されているラインも色や本数がバラバラ。実はそれ、ただのデザインではないのです。11月22日放送のCBCラジオ『石塚元章ニュースマン!!』では、愛知県建設業協会に所属している中部土木株式会社の小田さんが、意外と奥深いヘルメットの世界について解説しました。聞けばちょっと見方が変わる、そんなヘルメットの秘密を読み解いています。聞き手はCBC論説室の石塚元章特別解説委員と加藤愛です。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴くヘルメットの由来
小田「知ったら誰かにちょっと話したくなる、ヘルメットのお話をします」
事故や危険などから頭を守るために使うヘルメット。工事現場などで作業するスタッフがよくかぶっているのを見かけます。
小田「実はこのヘルメット、兵士の兜が由来となっているそうです」
戦いのときに狙われると最も危険なのは頭。古代ギリシャやローマの時代に、兵士の頭部保護のために青銅や革で頑丈な兜を作ったのがヘルメットの始まりなのだとか。ちなみに「ヘルメット」の語源は、古い英語の「ヘルム(兜)」に「小さな」を意味する接尾辞「-et」が付いたものです。
小田「我々も現場でよい建物やよい道路を作るために日々戦っているソルジャーなので、ヘルメットをしっかり着用して、かっこよく戦っています」
デザインが違う意味
ヘルメットをよく観察すると、同じ現場内でも色が違っていたりラインが入っていたり、もしくは入っていないことに気づきます。
小田「この違いはご存じですか?」
加藤「考えたことなかったですね…」
石塚「区別がつくからでしょうか」
工事現場では労働安全衛生規則などによりヘルメットの着用が義務付けられていますが、色やラインに関しては法律で決まっているわけではなく、どれも任意だそう。
小田「でもちゃんと理由があって。色は所属が一目でわかるように、ラインは仕事の効率を上げるためにデザインされているんです」
石塚「ラインで効率が上がる?」
ハテナマークでいっぱいの石塚と加藤。
安全のための工夫
ヘルメットの色やラインは役割や立場を表し、安全管理や円滑な作業に一役買っているとか。
小田「現場が大きくなれば大きくなるほど、複数の会社が同じ場所で働くことになるじゃないですか。そうすると当然働く人の数も多くなり、誰がどういった仕事をしているのか、パッと見ただけではわからなくなりますよね」
作業を依頼したいのに誰が担当なのかわからない。これでは指示を出す人も作業する人も困ってしまいます。
小田「ですからヘルメットが作業場ごとに色分けがしてあったり、もしくはラインの有無、本数でその方の役割や立場を表しているんです」
例えば赤色のヘルメットは責任者、白色は一般作業員、黄色は見学者や訪問者、と言った具合です。ラインの色で役割を、本数で職位を表すこともあるとか。
小田「これをやることによって工事がスムーズに進められるので、色やラインはとても重要な役割を果たしているんです」
ただし法的に定められているわけではないため、現場や会社によってルール設定は異なるようです。
青いヘルメットは平和の象徴
そんな話の中で、石塚はとある出来事を思い出したようです。
石塚「昔取材で海外へ行った時に、国連の人達はブルーのヘルメットを被っていたんですよ」
これは通称「ブルーヘルメット」と呼ばれ、国連が紛争当事国へ派遣する監視団および治安維持部隊が身に着けるものです。もしくはそういった事態の悪化や拡大を防ぐ活動に携わる人々のことを、そう呼んだりもします。
石塚「敵や味方が入り乱れている中で停戦監視に行っても、青いヘルメットを被っている兵隊さんは国連の監視員の人だって、一目瞭然なんですよね」
平和維持要員自身の命を守るものでもあり、同時に「みんな安全に」という願いが込められたヘルメットでもあるのです。このようにヘルメットには、安全に効率よく現場作業を進めるための秘密が隠されているそう。
小田「我々も顎紐と気持ちをしっかり占めて、安全に気を付けて作業に取り組みたいですね」
工事現場を通りかかったら、ヘルメットの色やラインに注目してみましょう。
(吉村)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。