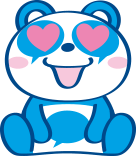甲子園の土を捨てた過去も。沖縄の甲子園史

第107回全国高等学校野球選手権大会、夏の甲子園は、8月23日にいよいよ白熱の決勝戦を迎えました。大注目の対戦カードは、西東京の日本大学第三高等学校と沖縄県の沖縄尚学高等学校。日本中が勝負の行方を固唾を飲んで見守りました。この日に放送されたCBCラジオ『石塚元章 ニュースマン!!』では、沖縄県における甲子園の歴史を紐解きました。CBC論説室の石塚元章特別解説委員が、沖縄県の辿った軌跡と甲子園との関係を掘り下げます。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴く沖縄と高校野球
沖縄尚学は、これまでに春の選抜大会では2度優勝していますが、夏の甲子園では初の決勝進出です。初めての優勝を目指す沖縄尚学に対し、日大三校は14年ぶり3回目の優勝を狙う対戦となりました。
沖縄県では2010年に決勝進出した興南高校以来、15年ぶりの夏の決勝戦となり、大きな盛り上がりを見せているようです。
沖縄は非常に高校野球人気が高く、地元の学校が出ているタイミングはみんなテレビを見ながら応援をするため、街中から人がいなくなるほどだとか。
さらに今年は決勝進出。那覇市内の航空会社は決勝前後の沖縄ー大阪の便を増やしたそうです。
戦後の沖縄では
そんな沖縄の学校が甲子園に出場するたびに、思い出すことがあるという石塚。
石塚「沖縄の学校って、最初の頃はなかなか甲子園に出場できなかったんですよね」
そもそも沖縄に初めて野球が伝わったのは1894年のこと。それから学校を中心に社会人にも少しずつ野球が根付いていく中で、戦争が激化。一時その文化は途絶えますが、戦後すぐに野球文化は復興します。しかし戦後の沖縄はアメリカの統治下におかれたため、1946年に再び開催されることとなった全国大会には参加できなかったのです。
石塚「それがだんだん出られるようになって、いろんな学校が少しずつ力をつけていく中で、初めて甲子園で優勝したのが今回決勝に臨んだ沖縄尚学なんです」
1999年に行なわれた春の選抜で、沖縄県の学校で初めて優勝旗を持ち帰ったのが沖縄尚学だったのです。
全員でウェーブ
その際にとても印象的だったエピソードがあるという石塚。
石塚「初めて沖縄の学校が優勝したので、応援に駆け付けていた地元の人たちは大喜びして。観客席では自然発生的にウェーブが起こったんです」
ウェーブとはスタジアムで観客が縦列順に立ったり座ったりすることで、遠目に見たらまるで波が立っているように見えるという現象です。
石塚「沖縄尚学の応援席だった1塁側から流れていったウェーブがそのまま3塁側まで行くんですが、そこにはその時負けた水戸商業高校のファンや関係者が座っているわけです。でもウェーブは途切れないで、ずっと続いていくんです」
対戦相手だった水戸商業側の人達も、沖縄尚学の初優勝に健闘を称えて、一緒になってウェーブをしたのだとか。本来なら悔しさで唇を噛む立場であるはずなのに、負けた相手にも拍手を送る、まさにスポーツマンシップ溢れる感動的な出来事だったようです。
捨てられた土
石塚「もうひとつ、沖縄と甲子園に関するエピソードがあります」
沖縄は1958年、初めて甲子園出場を果たします。その時甲子園の大地を踏みしめたのは朱里高校。ですが生憎優勝は出来ず、1回戦で敗れたそうです。
石塚「甲子園で敗れると、みんな土を持って帰りますよね。この時の朱里高校の生徒たちも土を持って帰ろうとするんですが、当時の沖縄はまだアメリカの統治下なんです」
すると法律的には当時の沖縄はアメリカだったということで、つまり外国なのです。外国であるということは、出入りの際に荷物の検疫があるということ。
石塚「外国の土は持ち込めないんですよね。港に着いた時に、全部海に捨てなくてはならなかったんです」
選手たちにとっては一生の思い出となるはずだった大切な土が、無情にも海に流されてしまうのはどんなにつらい出来事だったことでしょう。沖縄の高校と甲子園との関係を紐解くと、そこには歴史を感じさせるようなエピソードがあったのでした。
(吉村)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。