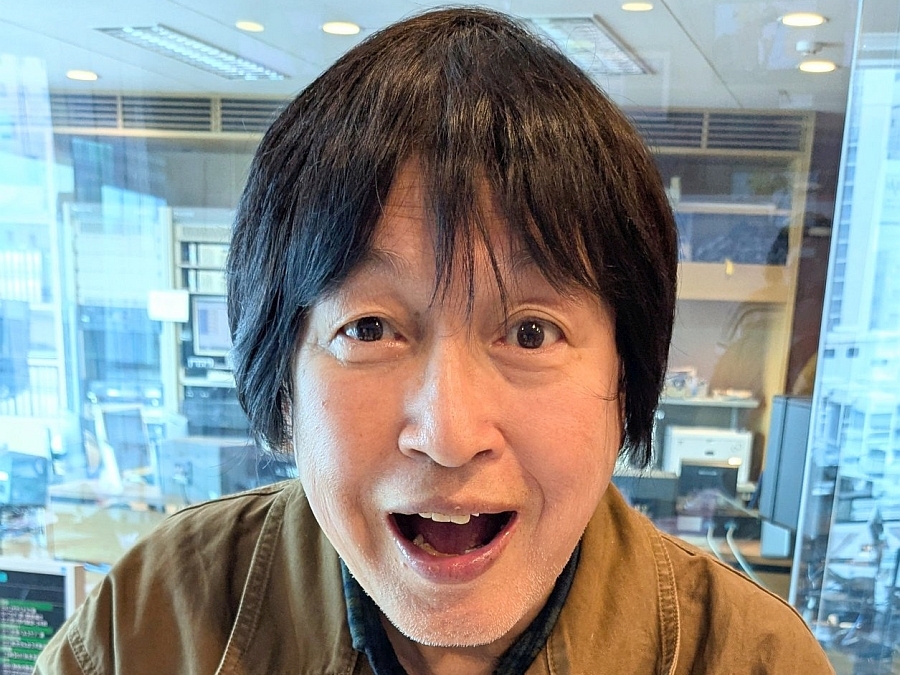フェアトレード市場、10年で倍増も生産者支援は不十分?

最近定着してきた「フェアトレード」。「公平・公正な貿易」という意味です。5月は「フェアトレード月間」として、さまざまな企業や団体が啓発活動を行っています。ちなみに「フェアトレードの日」は5月第2土曜日です。5月21日放送のCBCラジオ『つボイノリオの聞けば聞くほど』では、つボイノリオと小高直子アナウンサーがフェアトレードについて取り上げました。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴く国内市場が10年で倍増
フェアトレードが意味するものには、人と環境に配慮して生産されたものを適正な価格で取引することの他、原材料生産者の人権を守る生活向上や、持続可能な栽培などを目指すことなども含まれています。
つボイ「チョコレートやコーヒーなど、フェアトレードの認証マークが付いた商品を見かけますよね。で、手に取って見ると『お、高いな』って思いつつ、これが本来の適正価格なんだ、と考えるようになってきました」
小高「確かに、フェアトレードもかなり定着してきましたよね」
5月1日、普及・啓発を行っている団体の1つ、認定NPO法人フェアトレード・ラベル・ジャパンでは、この10年で日本国内のフェアトレード市場が倍増していると発表しました。
つボイ「10年で倍増ですか。買う人の意識がかなり変わってきたということですね」
生産者の収入アップはまだまだ
小高「今までは安いものを追求してきたんだけど、ふと『この安い価格は誰かが無理した結果なんじゃないか』って考えが広まったのならいいこと。
ただ、これが生産者の収入向上につながっているかについては、、まだまだ結びついていないのが現状なんだそうですよ」
近年異常気象による干ばつ・大雨や洪水などで、収穫量が著しく低下した作物がいくつもあるそう。昨年は、カカオが足りないと大きな話題になりました。
物流コストの上昇や管理コストの高騰で、もともと高めの価格設定となっています。しかし現実には生産農家全体の収入アップまではカバーしきれていないようです。
今回の発表では、人権問題の解決や開発途上国の支援が主だったフェアトレードが、環境保護・気候変動対策にも大きく関わっていることが示唆されました。
生産者の生活が向上すれば、次の段階として異常気象に適応できるような農業を整えたり、環境に配慮した農業ができるようになると考えられています。
つボイ「確かに自分に余裕がなければ、環境に配慮したり気候変動対策をしたりするという気持ちは出てこないですね。生産者に収入が十分に配分されることは、やはり重要なことだと思います」
環境保護や異常気象対策
フェアトレード・ラベル・ジャパンでは、現在「ミリオンアクションキャンペーン2025」を開催しています。
フェアトレード商品を購入したことをSNSに投稿することで、途上国の生産者への寄付につながるそうです。
小高「SNSで検索してみると、多くの方がキャンペーンに参加されていることがわかります。少しだけ意識してみるといかもしれませんね」
フェアトレード商品を買う・ハッシュタグを付けてSNSへ投稿する・イベントに参加するなど1アクション=1円が途上国への寄付になります。
投稿する時は、「#Fairtrade2025」というハッシュタグをお忘れなく。
なお今回のキャンペーンでは300万アクションの達成を目指しているとのことです。
(葉月智世)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。