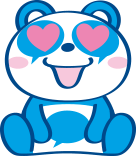“民意”が漂流する夏、退陣?続投?揺れ続ける石破政権から考える沖縄への思い

参議院選挙が終わって2週間以上が経った。しかし、日本の政治が一向に落ち着かない。選挙結果で、自公政権の過半数割れという結果は出たのだが、石破茂政権が退陣することは現時点なく、その賛否を巡って自民党内も揺れている。両院議員総会も開催されるが、この揺れはまだ続きそうな様相だ。
“民意”は現政権に「NO」
2025年(令和7年)7月20日に投票が行われた参議院選挙の投票率は、58.51%だった。このところ5割を下回る時もある低投票率だったが、今回は3連休の中日にもかかわらず、前回3年前の参院選を7ポイント近く上回った。止まらぬ物価高をはじめ、自民党のいわゆる“裏金”問題の余波も続いていて、この選挙は早くから「政権選択選挙」と位置づけられてきた。結果は「自公政権が過半数割れ」となり、石破政権は衆議院と共に両院で過半数を失った。すなわち「現政権NO」という結果が“民意”だった。
続投を表明したリーダー
“民意”とは、世論が形になったもの、すなわち国民の意思である。今回の参議院選挙は投票率も上がり、そんな中で示された“民意”なのだが、それがスルーされている。自民・公明合わせて過半数維持となる50議席を目標に掲げていた石破総理は、すべての開票が終わる前から「続投」の意志を表明した。その決断に驚いた人も多かっただろう。退陣するべきだ、いや辞める必要はない、という自民党内でのやり取り、それは永田町の外にも波及している。石破政権に突きつけられた“民意”の行方が漂流する中、ふと沖縄のことを思った。
沖縄での住民投票結果
「一体何度、自分たちの意思を示せばいいのか」。この言葉を聞いたのは、2019年(平成31年)2月のことだった。米軍普天間飛行場の移設先として、名護市にある辺野古の海の埋め立て問題をめぐって、その是非を問う県民投票が行われた。半年前の知事選では「埋め立て反対」を訴えた玉城デニー現知事が当選して、その時すでに“民意”は示されていた。住民投票の投票率は52.48%、この内の7割を上回る43万票が「埋め立て反対」に投票した。知事選で玉城デニー知事が獲得した39万票余りを超えた数だった。
無視され続けた沖縄の“民意”

しかし、住民投票から1か月たった3月末に、辺野古沿岸部の新たな区域に土砂の投入が始まった。それが沖縄の“民意”に対する回答だった。政府は一貫して「普天間飛行場の危険除去と返還に向けて、今後も辺野古の埋め立て工事を進める」という姿勢を続けた。その後、同じ2019年は、衆議院沖縄3区の補欠選挙、さらに参議院選挙と国政選挙が続いた。いずれも「埋め立て反対」を訴えた候補が当選したが、工事は粛々と進められた。立ち止まって考えることもなかった。「一体何度、自分たちの意思を示せばいいのか」。2025年夏の参院選を終えて、沖縄から離れたところで暮らしながらも、あらためてこの言葉の重さを噛みしめる。
現政権のけじめとは何?
“民意”は時に移ろいやすい。時間の経過と共に姿を変える時もある。投票日から月も替わり、世論調査の結果も次第に「石破総理は辞任すべきではない」という声が増えつつある。今回の参院選で示された“民意”はどうなるのか。選挙結果によって「NO」とされた現政権は、どうけじめをつけるのか。石破総理が再びリーダーとして歩むにしても、やはり一度はリセットが必要なのではないか。
“民意”の行方と政治離れ
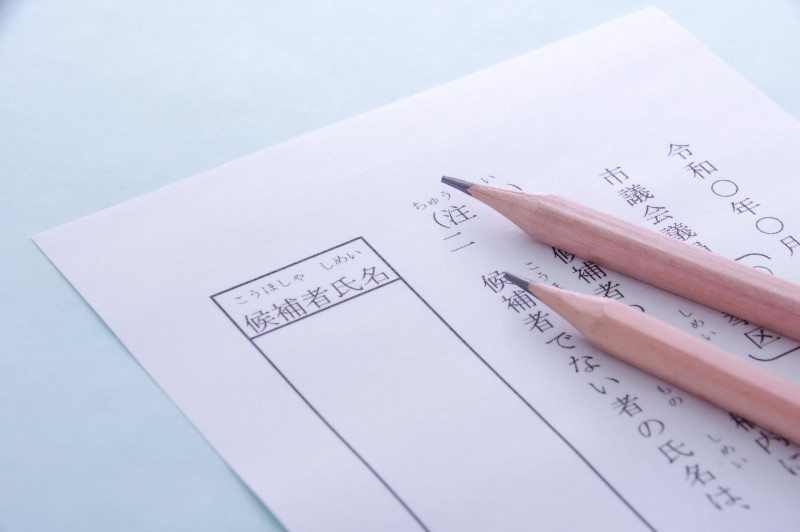
心配なのは、せっかく投票に行った人が増えたのに、そこで示された意思が浮遊していることを、国民全体が目の当たりにしていることである。選挙での投票は民主主義の根幹であり、それを守るためにも選挙結果の“民意”は尊重されなければならない。「結局、何も変わらない」と政治離れが進むことは食い止めなければならない。「一体何度、自分たちの意思を示せばいいのか」と話していた沖縄の人たちは、どんな思いで、今回の参院選後の政局を見つめているのだろう。
国の政治だけではなく、昨今、地方自治体でもトップが「辞める、辞めない」の渦中に身を置くことが多くなっている。リーダーにとって、身は“置く”ものではなく“処す”ものである。戦後80年目の夏、「けじめ」を重んじた日本という国の変貌ぶりが、不快な暑さをますます倍増させているようだ。
【東西南北論説風(611) by CBCマガジン専属ライター・北辻利寿】