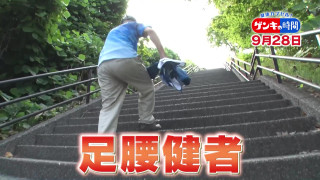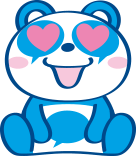最悪寝たきりに!?「いつのまにか骨折」…「骨」が脆くなる原因は?骨の健康を守る方法

身近な健康問題とその改善法を、様々なテーマで紹介する番組『健康カプセル!ゲンキの時間』。
メインMCに石丸幹二さん、サブMCは坂下千里子さんです。
ドクターは、済生会横浜市東部病院 整形外科部長 骨代謝センター センター長 医学博士 福田健太郎先生と医長 山内俊之先生です。
今回のテーマは「〜折れているのに痛くない!?〜いつのまにか骨折とは?」
あまり痛みがない骨折をご存知ですか?その1つが「いつのまにか骨折」。いつのまにか骨折とは、年をとって脆くなった背中の骨に何らかの圧力がかかり潰れてしまう圧迫骨折のこと。骨が弱った状態を放置すると、最悪の場合寝たきりの状態を引き起こし、認知症につながる恐れもあるそうです。そこで今回は、骨の健康を守る方法を専門医に教えてもらいました。
「いつのまにか骨折」とは?

いつのまにか骨折は、脆くなった状態の骨が日常生活の行動で潰れてしまう背骨の圧迫骨折のこと。くしゃみ・尻もち・前屈みでの作業など、背中に圧力がかかることで引き起こされるそうです。
「いつのまにか骨折」が増えている!?
高齢化社会に伴い、いつのまにか骨折も増加傾向にあるといいます。多いのは中高年の女性ですが、男性に起こることもあるのだとか。圧迫骨折の最初の状態は、脆くなった骨が崩れるような形でわずか1〜2mm程度潰れるので、痛みが出にくく症状だけでは気付きにくそうです。
いつのまにか骨折のさらなる恐怖「連鎖骨折」「認知症」
背骨は24個の骨が積み重なってできており、1つ1つに常に圧力がかかっています。そのため、1つの骨が折れた状態だと、他の骨にさらなる圧力がかかり、連鎖的に骨折を引き起こしてしまいます。しかも、背骨が折れてしまうと寝たきりの状態を引き起こし、人とのコミュニケーションが減少。認知症を引き起こす可能性もあるそうです。
いつのまにか骨折の原因「骨粗しょう症」
いつのまにか骨折の原因となるのが「骨粗しょう症」。骨粗しょう症は、骨の密度が減少してスカスカになったり、骨の質が低下することで骨が脆くなったりして骨折しやすくなる病気。そのため、1つ目の骨折が見つかったときにしっかりと骨粗しょう症の治療を行い、2つ目の骨折を防ぐことが大切だそうです。
骨が脆くなる原因は?
骨では、古い骨を壊す「破骨細胞」と新しい骨を作る「骨芽細胞」が働いています。破骨細胞が古くなった骨を溶かし、その溶けた部分を埋めるように骨芽細胞が新しい骨を作り直すことで常に生まれ変わる仕組みになっているのだとか。ところが、加齢などが原因で破骨細胞が活発になると、骨芽細胞の骨を作る働きが追い付かず、脆く弱くなってしまうそうです。
<骨密度を下げるもう1つの原因>
加齢以外に骨密度を下げる原因の1つが「女性ホルモンの低下」。本来、女性ホルモンは骨を破壊する破骨細胞の働きを抑えますが、閉経を迎えると女性ホルモンが減少。破骨細胞の働きが活発になり、骨の再生が間に合わなくなるのだとか。そのため、閉経後の女性は骨粗しょう症が特に起こりやすいと考えられているそうです。
女性だけでなく男性も注意!骨粗しょう症の原因「骨質」
骨粗しょう症患者のうち、4人に1人は男性というデータがあります。男性の場合は骨の密度よりも骨の質の低下が原因で骨粗しょう症になることが多いそうです(※男性だけでなく女性も骨質の低下は起こります)。
<骨密度だけでなく骨質も大事!>
骨は、カルシウムなどのミネラル成分とコラーゲンなどのたんぱく質で形成されています。骨の構造を鉄筋コンクリートの建物に例えると、カルシウムはコンクリートで、コラーゲンは鉄筋。建物は、コンクリートだけでは頑丈に建てることができません。それと同じように骨を丈夫にするには、カルシウムで骨密度を増やすだけでなく、コラーゲンで骨質を高めることが大切だそうです。
<骨質が悪くなる原因は?>
ホルモンの低下だけでなく、運動不足・栄養不足・不規則な生活・過度な飲酒なども骨の形成を損なう働きがあるのだとか。骨質を高めるためには、健康的な生活習慣とバランスよく栄養を摂取することが大事だそうです。
あなたの骨は大丈夫!?骨粗しょう症セルフチェック

<骨粗しょう症セルフチェック(1)>
下記の項目に2つ以上当てはまる場合は、将来的に骨密度が下がっていく恐れがあります。
□乳製品や魚 大豆製品の摂取が週2回以下
□アルコールを週5日以上飲む
□筋トレや体操などの実施が週1回以下
<骨粗しょう症セルフチェック(2)>
下記の項目に当てはまる場合は、骨粗しょう症を発症している可能性があるのですぐに検査を受けてください。
□昔より背中が丸まってきた
□20歳の頃と比べて2cm以上背が縮んだ
いつのまにかの骨折を防ぐ3つの柱(1)検診
代表的なのは、骨密度検査。骨に含まれるミネラル量などを測定する検査で、検査時間は10分程度。検査結果により骨粗しょう症の診断や骨の健康状態を評価します。自分の骨密度を知ることで骨への意識が高まるので、検診を受けることがいつの間にか骨折を防ぐ大事な一歩となるそうです。
<骨の強さを示す値「YAM(ヤム)値」>
骨密度検査では若い世代の健康な同性の平均骨密度を100%とした時、被検者は何%かをYAMという値で比較します。80%以上が正常で70%以下だと骨粗しょう症と診断されるそうです。
いつのまにかの骨折を防ぐ3つの柱(2)食事
骨の材料に大事なのは「カルシウム」と「たんぱく質」ですが、「ビタミンD」「ビタミンK」も大切な栄養素。ビタミンDは腸でカルシウムを吸収しやすくし、ビタミンKはカルシウムを骨にしっかり定着させます。カルシウム・ビタミンD・ビタミンKの3つの栄養素は、骨のゴールデントライアングルと言われ、あわせて摂取することで丈夫な骨を作ることができるそうです。
<骨に大事な食材>
ビタミンDを多く含む食材は、魚・キノコ類(※日光浴もビタミンDを生成します)。ビタミンKは、納豆やほうれん草・ケールなどの青菜に多く含まれています(※ワーファリンなどの血液凝固防止薬を服用中の人はビタミンKの摂取について主治医にご相談ください)。骨の土台となるコラーゲンを作るたんぱく質は、乳製品・卵・肉・魚などに多く含まれているそうです。
<食事のポイント「摂取する時間>
骨吸収・骨形成は寝ている間に促されているそうです。そのため、夕食や寝る前に上記の栄養素を摂取すると効果的なのだとか。4つの栄養素をバランスよく摂ることで、骨の健康を保ったり、脆くなった骨を強くしたりすることができるそうです。
いつのまにかの骨折を防ぐ3つの柱(3)運動
いつのまにか骨折を防ぐための3つの体操をご紹介します。
<(1)背骨を正しい位置へ「背筋ピン体操」>
▼イスに浅く腰かけて骨盤を起こし 背筋を伸ばす
▼両手を肩の高さに上げて ひじを後ろに引き 胸を大きく開き 息を吐きながら5秒止める
▼上記を1日5回 朝・昼・晩行う
※無理のない範囲で行いましょう
背筋をまっすぐにすることで、背骨を正しい位置に戻す効果が期待できるそうです。
<(2)インナーマッスルを鍛える「おなかピタ体操」>
▼息を吐きながら おへそを背中にくっつけるようにへこませる
▼へこませた状態で 手を前であわせ 軽く左右の足上げを10回行う
※無理のない範囲で行いましょう
足上げを行う時は、身体が反らないように要注意。この体操で背筋を維持するためのインナーマッスルを鍛えることができます。一度落ちた骨密度を上げるのは簡単ではないですが、周りの筋肉を鍛えることで天然のコルセットの役割を果たし、弱った骨のサポートをしてくれるそうです。
<(3)刺激で骨の形成を促す「かかとストン体操」>
▼腰に手を当て まっすぐ立ち つま先に体重をかける
▼床を押すようにしてかかとを軽く持ち上げストンと落とす
※無理のない範囲で行いましょう
ストンという刺激が大腿骨や背骨に伝わることで、骨を強くする働きがあると言われています。ふらついてしまう場合は、イスの背もたれなどを持ち転倒を予防しましょう。
(2025年11月23日(日)放送 CBCテレビ『健康カプセル!ゲンキの時間』より)
番組紹介
ニッポンの皆様に健康生活を!この言葉をキーワードにすぐに役立つ健康情報をお伝えします。「人」「家族」の未来を創り出す、CBCテレビの健康情報番組。