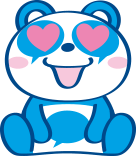降水量ってどこから危険?予報外したら落ち込む?気象予報士が様々な疑問に回答

10月13日放送の『CBCラジオ #プラス!』には、日本気象協会の立岩洋輔さんがゲストとしてスタジオに出演し、気象に関する話題を解説しました。リスナーから寄せられた気象の仕組みや予報士の仕事など、幅広い質問に立岩さんが答えます。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴く危険な降水量は何ミリから?
まず寄せられたのは、雨に関する疑問。
「降水量が何ミリと言われてもピンとこないんですが、何ミリぐらいから危険なんですか?」(Aさん)
この疑問に対して立岩さんは、気象庁が雨の強さを降水量で定義していることを紹介。
10~20ミリが「やや強い雨」、20ミリ以上で「強い雨」、30ミリを超えると「激しい雨」とされており、この30ミリを超えるあたりから災害のリスクが高まります。
また、30~50ミリの雨になると「バケツをひっくり返したような雨」と言われ、道路がまるで川のようになり、車の運転にも危険が伴うように。
さらに、50ミリ以上で「非常に激しい雨」、80ミリを超えると「猛烈な雨」と呼ばれ、こうしたレベルになると災害が発生する可能性が非常に高くなるとのこと。
数字が30ミリ以上になった場合は注意が必要です。
地域ごとの雨の傾向
雨に関して、このような質問も届きました。
「名古屋港付近に行くと、雨が降っていないことが多い気がする」(Bさん)
「同じ県内でも、雨が降りやすい地域とそうでない地域があるのでは?」(Cさん)
雨雲が発生するには“風の収束”という現象がひとつのきっかけになります。
これは、異なる風向きの風同士がぶつかり合い、行き場を失った空気が上昇して雲を作るというものです。
沿岸部ではこの風の収束が起こりにくい場合があるとされ、名古屋港のような場所では、若狭湾からの風が吹き抜ける影響もあり、雲が発達しづらい傾向にあると考えられます。
また、愛知県と岐阜県の県境付近では風の収束が起こりやすく、名古屋の北部などでは局地的な雨が発生しやすい地域があるということです。
偏頭痛と天気の関係
続いては人の感覚についての質問です。
「妻が『今日は偏頭痛がないから雨は降らない』と言ったのが当たったが、こうした体感による予測は信じられるのでしょうか?」(Dさん)
これに対し立岩さんは、「気象の変化と体調の関係には一定の関連性がある」と述べます。
天気が変わる際には気圧の変化が伴い、晴れの時には高気圧、雨の時には低気圧になります。
こうした気圧の変化が、人によっては片頭痛や体調不良の引き金になることがあるのです。
そのため「今日は頭痛がしないから雨は降らない」といった勘は結果的に的中することもあり、人間の感覚にも一定の根拠があることを認めました。
「梅雨前線」と「秋雨前線」
さらに「梅雨前線と秋雨前線の違いは何か?」という気象用語に関する質問も。
これはどちらも,異なる空気の塊がぶつかり合う境目という点では同じですが、発生する季節や空気の種類によって名称が異なるそうです。
梅雨前線は「春の空気」と「夏の空気」がせめぎ合うことで発生し、秋雨前線は「夏の空気」と「秋の空気」のぶつかり合いによって発生します。
つまり、前線の基本的な構造は同じでも、発生するタイミングや空気の性質によって名前が変わるとのこと。
天気予報士の苦悩とやりがい
最後は、気象予報士という職業についての質問も寄せられました。
「天気予報が外れたとき、落ち込んで眠れなくなったりするのですか?」(Eさん)
立岩さんの場合、予報が外れてしまうことはあるものの、原因を振り返って分析し、次に生かすことを重視し、必要以上に引きずらないようにしているとのことです。
「気象予報士としてやりがいを感じる瞬間は?」(Fさん)
これには「日々の天気を伝えるだけでも結構楽しくて」と一段と明るく回答。
実は前職がシステムエンジニアだった立岩さん。自然を相手にしている今の仕事に対して充実感を感じているそうです。
この日は専門的で難しいと思われがちな気象の話。立岩さんの解説を通じ、日々の暮らしに直結する天気のことを、改めて身近に感じました。
(ランチョンマット先輩)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。