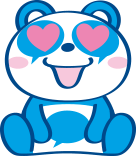負担なく受け取ってもらうために見直そう!死亡保険金受取人見直しの重要性とは

昨今、少子高齢化で中小企業・小規模事業者の後継者難が大きな経営課題の一つとなっています。「人生100年時代」の今だからこそ、元気なうちに資産の管理やスムーズな承継について考えていく必要性が高まっているのです。CBCラジオ『北野誠のズバリ』「シサンのシュウカツにズバリ」では、事業承継と資産承継について専門家をゲストに学んでいきます。9月17日の放送では、「死亡保険金受取人の重要性」について北野誠と松岡亜矢子が三井住友トラストグループ 三井住友信託銀行 株式会社名古屋営業部 財務コンサルタント杉山泰則さんに伺いました。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴く設定した死亡保険金の受取人が…
今回は死亡保険金受取人の重要性について。
北野「死亡保険金受取人が先に亡くなって、そのままの場合はどうなりますか?」
杉山「死亡保険金受取人の法定相続人に法定相続割合が一般的です。ただし、被保険者の遺族に均等割合等の例外もあります。保険会社の約款に拠ります」
読むのが嫌になる分厚く細かい字でたくさん書かれた約款。一見、ものすごく問題になるようには思えないのですが…
杉山「実際に事例をお話しします。お子さまがいらっしゃらないご夫妻が死亡保険金の受取人をお互いにしていました」
妻が先に亡くなった後も、主は自身の死亡保険金受取人を妻から変えないまま亡くなってしまいました。こうしたケースは決して珍しくありません。
受取人を適宜変えないことで起こる悲劇
本件では亡き妻の法定相続人に権利が移ることになりました。
北野「法定相続人って何人くらいいたんですか?」
杉山「相続人は10名いらっしゃいました。手続自体も面倒になりましたが、外国にいらっしゃる等で連絡がつかない方もいたため、最終的に保険金請求は諦められました。こうなると、何のための保険だったのかと思ってしまいますよね」
では、深く考えずに死亡保険金受取人を決めて困ることとしては、どんなことが挙げられるでしょうか?
「主に2つある」と杉山さん。
まずひとつ目は、死亡保険金受取人を相続人以外にしていた場合。例えば、法定相続人であるこどもがいるのに、法定相続人ではない孫にした場合などです。
そのこと自体悪いことではありませんが、死亡保険金の非課税枠(法定相続人×500万円)が利用できなくなってしまいます。
贈与の枠を超えて遺贈になるケースも
ふたつ目はちょっと複雑です。
杉山「お孫さんやお子さまの配偶者等の法定相続人ではない方に贈与していた場合で、そのような方を死亡保険金受取人にしてしまった場合です」
これもこのこと自体が悪いわけではありません。
しかしながら、相続または遺贈により財産を取得した人が相続開始前7年以内(令和5年までの贈与では3年以内)に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、その贈与を受けた財産も、相続税の課税対象になります。
北野「死亡保険金受取人になったことで、遺贈による財産取得になるんですか?」
杉山「その通りです。相続人ではないお孫さんなどに贈与をしていているため、その贈与については、最近の贈与であっても相続税の課税対象にならないと思っていたところ、死亡保険金の受取人になったことで相続税がかかるかもしれない事態になるというわけです」
2つの事例から、死亡保険金受取人が亡くなったのにそのままにしておくと、死亡保険金請求手続がものすごく面倒になったり、事実上受け取れなくなる場合があることがわかります。
北野「なんとなく死亡保険金受取人を決めておくと、非課税枠を使えなくなったり、かからないと思っていた相続税がかかってしまうなど、想定外のことが起きるかもしれないということですね」
もし、長らく死亡保険金受取人を見直していないという方は、ぜひ一度確認してみてほしいと締めくくりました。
(葉月智世)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。