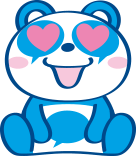修行僧の気持ちになるとご飯も喉を通らない理由とは?興福寺の千手観音

毎週木曜日の『ドラ魂キング』では、CBCの佐藤楠大アナウンサーが仏像に関するトピックを紹介します。9月18日の放送で紹介したのは、奈良県興福寺の木造千手観音菩薩立像。佐藤が仏像好きになったきっかけとなったこの仏像、いったいどんな特徴があるのでしょうか?
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴く千手観音とは?
佐藤「男のロマン!派手で豪華で大きくて装飾も多くてカッコいいんです。しかもいろいろな仏像の良さが詰まっていて、『へえ、なるほど』が多いものになっています」
まずは千手観音の基本的なことから説明していきます。
観音様はいろんな姿をしているそうです。如意輪観音、十一面観音、不空羂索観音…。そのひとつが千手観音。
千手観音を仏像で表現した時、一般的な千手観音像は、名前と違って腕が千本ないそうです。ではいったい何本あるのでしょうか?
一般的には42本。身体の正面で合掌しているので左右で2本。それ以外に左右、20本ずつの腕が生えているそうです。
千の手?千の世界?
仏教の宇宙観では、天上界から地獄まで25の世界があり、その世界を1本の腕で救うという意味で25×40。
千の手を持つからではなく、千の世界を救うから千手観音という考え方もあるんだとか。
佐藤「ただこれ、平安時代にそのような作り方が増えてきただけで、実際に日本にも千本腕があった千手観音もいるんです」
佐藤が調べたところ、大阪の葛井寺、奈良の唐招提寺、京都の寿宝寺に腕が千本ある千手観音像があるそうです。
佐藤「あとは作るのが大変だから、いろんな考えが普及して、ちょっと楽しようかと思ったかな?とも思います」
これはあくまで佐藤の意見です。
「全部乗せ」の観音
佐藤「1本1本の手に注目してほしいんです。全部違うものを持っています」
左右に20本ずつの手には、杓、剣、弓、矢、花などを持っており、そのひとつひとつに意味があるとか。
例えば不空羂索観音には羂索(けんじゃく。人々を救う縄のこと)を持った手もあります。
佐藤「さらに、いろんな要素の詰め合わせと点で、千手観音の頭に注目してもらいたい。十一面なんですよ。頭の後ろにも大きく笑っている面があるんです」
これは十一面観音の様式。
佐藤「いろんな観音様の要素を詰め込んでいるがゆえに、観音様の中でも救う力が最強格だと言われています」
ある教えでは、蓮華の上に立つ姿から「蓮華王」と呼ばれるほど人を救済する力があるそうです。
縦横にすごい存在感
今回紹介する興福寺の千手観音は鎌倉時代に作られた国宝。腕は42本ですが、像の高さが520.5センチとかなりの大きさ。
縦に大きいだけではなく、左右に40本の手が生え、幅もかなりあってものすごい迫力と存在感だとか。
展示場所は興福寺の国宝館で、以前紹介した阿修羅像もある場所です。
佐藤「最近改修工事されて、仏像の荘厳さ、大きさをより強調するライトアップになっているので美しいですよ。生でぜひ見て欲しい」
念のため行かれる方はホームページを確認してください。
佐藤「国宝館ぐるっと回ると、いろんなカッコイイ仏像がありますのでぜひ見ていただきたい」
ご飯が喉を通らない?
現在国宝館が建っている場所は、もともと興福寺の食堂(じきどう)。つまり僧侶たちがご飯を食べる場所だったそうです。
そこに本尊として置かれていたのが、この木造千手観音菩薩立像です。
佐藤「ご飯を食べる場所に、5メートル超えのこんな金ピカの仏像いたらどうですか?」
当時のお坊さんは、厳かな場所で修業をし、巨大な千手観音に見られながらご飯を食べていたわけです。いったいどんな気持ちだったのでしょうか?
佐藤「空気感がいい意味で厳かで重々しいので、私だったらご飯食べられない(笑)。そこも体感していただければと思います」
(尾関)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。