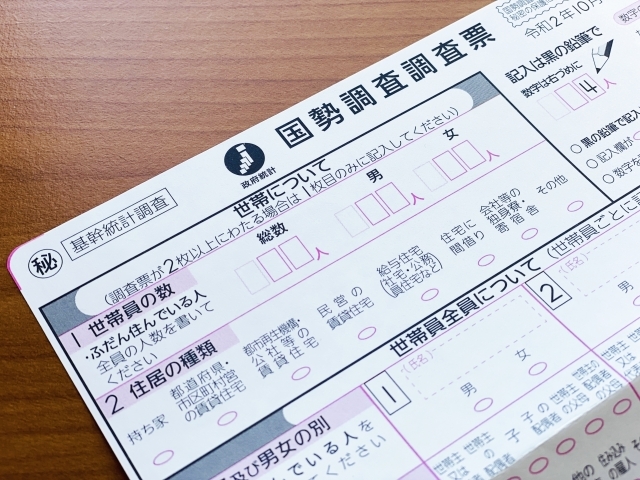ぼったくり被害を防ぐためにはどうすればいい?

名古屋しの繁華街・栄地区の飲食店で起きている「ぼったくり被害」の相談件数が8月末時点で180件となり、年間の最多を更新しました。被害者の9割が当初の説明と異なる高額な料金を請求されるといった客引き経由の来店です。愛知県警は9月から客引き行為への取り締まりを強化しています。9月16日放送の『CBCラジオ #プラス!』では、ぼったくり被害増加についてアディーレ法律事務所弁護士の正木裕美先生に尋ねます。聞き手は光山雄一朗アナウンサーです。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴く請求額が大幅に増加
ぼったくりの相談件数が年間最多を更新し、県警は取り締まりを強化しています。
正木「コロナ前は多少減少傾向にありましたが、コロナで飲食店がお休み。コロナ明けになって急増しているという状況です。
2017年で51件、そこから2019年までは1件とかなり減少していましたが、2023年には127件、昨年は147件と急増しています。
被害額も、2023年で6600万円あまり。昨年は9000万円あまり。今年の8月末で1億2000万強と大幅に増加してしまっているという状況です」
客引きを担う業者の存在
なぜ、こんなに増えているのででしょうか?
正木「はっきりとはしてないですが、少なくとも旅行客の移動が増えたということで被害者も県外客の方が多いです。
県警の発表によれば、ぼったくりは客引き経由で発生することが主ですが、いまお店側が客引きをしないで、客引きを担う業者がいて、そこに委託して客引きを行なってもらう形がメインになっています。
そこの団体が得るお金はひいた客に対するお金なので、できるだけ客をひいた方がいいです。そうすると正式な料金を提示してしっかりやるより、とりあえず客を入れることを優先してしまう、遵法意識が低い客引きが増えています」
愛知県のぼったくり防止条例
ぼったくりを取り締まる法律はあるのでしょうか?
正木「一般的に飲み屋さんは風営法という法律に基づいて営業しています。その法律では料金はちゃんと表示しなくてはいけないという規定はありますが、不当な料金、法外な料金を請求する独自の規定はないですし、違反した場合の刑罰もありません。
ということで、法律ではなく、愛知県のぼったくり防止条例があり、基本的にこちらでぼったくりは摘発されています」
料金の表示義務などの規定
この条例にはどんなことが定められているのでしょうか?
正木「料金の表示義務をしなければいけない、不当な勧誘などの禁止、料金の不当な取引の禁止、違法な客引きを受けたお客さんを立ち入れさせてはいけないという形で実行的な規定をしています。
特別地域が定められていて、名古屋の錦三丁目、栄の一部の周辺、飲食店が多い地域ですが、そういう地域でのぼったくりの罰則を厳しくしています。
こういう地域でぼったくった場合は六か月以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金を科するという形で、問題が起こりやすい地域での処罰を厳しくしています」
やむを得ない時はカード払いに
被害に遭ったときは、どう対応すればいいでしょうか?
正木「ベストは『払わないこと』です。払うとその後いろいろなやりとりが発生しますし、お金が返ってこないこともあるので、支払いを拒否する。
必要であれば、警察などに連絡したり、やりとりを録音録画したり、なんらかの証拠が残るように動くことが大切ではあります。
実際、そうはいっても怖い方に囲まれて支払い拒否を強く言うのは難しい、連絡をさせてもらえないというケースはあります。どうしても払わなくてはいけない状況でしたら、現金ではなく、クレジットカードで払っていただければと思います。
現金だとそのあとの取戻しが難しいですが、クレジットカードの場合はカード会社に連絡して支払いの停止を求めることができます。
いったんカードの支払いが止められるので、お金が取られてしまって戻ってこないというリスクが避けられます。最悪のケースではできればカードで支払うことがおすすめです」
(みず)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。