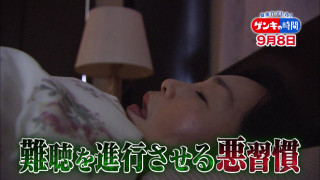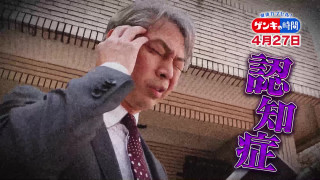あなたはいくつ当てはまる?「聞こえの悪さ」チェック…認知症に影響!?耳の衰え“ヒアリングフレイル”を予防する方法
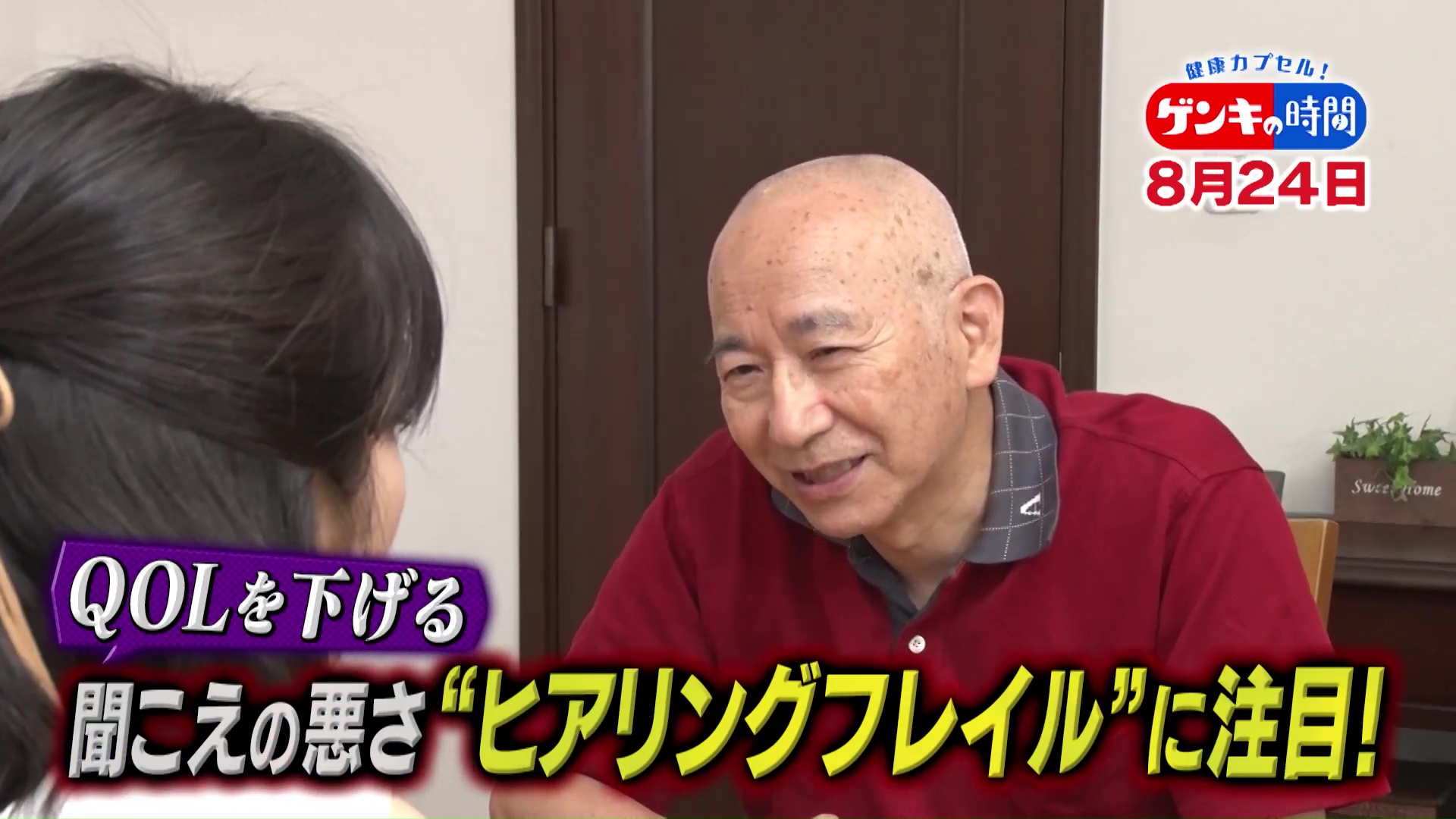
身近な健康問題とその改善法を、様々なテーマで紹介する番組『健康カプセル!ゲンキの時間』。
メインMCに石丸幹二さん、サブMCは坂下千里子さんです。
ドクターは、国立病院機構 東京医療センター 人工内耳センター長
耳鼻咽喉科科長 広報室長 医学博士 南修司郎先生です。
今回のテーマは「〜聞こえの悪さから認知症に!?〜耳の衰え“ヒアリングフレイル”」
今注目のキーワード「ヒアリングフレイル」をご存知ですか?ヒアリングフレイルとは、加齢で聴覚機能が衰え、生活の質が低下した状態のこと。コミュニケーションに支障をきたし、社会的な孤立や心理的ストレスを引き起こしてしまうそうです。実際、耳の聞こえが悪い人は50歳を過ぎたあたりから徐々に増え始め、65歳からは急激に増えるのだとか。そして、聞こえの悪さを放置していると認知機能の低下を招き、結果的に認知症を引き起こす可能性もあるといいます。そこで今回は、聞こえの悪さの原因やヒアリングフレイルを予防する方法などを専門医に教えてもらいました。
ヒアリングフレイルについて

フレイルとは、年齢とともに筋力や心身の活力が低下し、介護が必要になりやすい健康と要介護の間の状態。ヒアリングフレイルとは、フレイルに加えて聞こえの問題が起こることによって、コミュニケーションに支障をきたしたり、社会的孤立や心理的ストレスを招いたりして生活に支障が出ることを指します。さらに、音の刺激など外からの情報量が減ると、脳が萎縮したり神経細胞が弱まったりして、認知症の発症に影響すると言われているそうです。
<コミュニケーションの低下を防ぐには?>
聞こえの悪さによるコミュニケーションの低下を防ぐには、自分で聞こえの悪さを認識することと、周りの人の理解が大切だそうです。
<聞こえの悪い人との会話のポイント>
聞こえの悪い人と接する際は、下記のポイントを意識すると良いそうです。
(1)ゆっくりハッキリ話す
(2)顔(口元)を見せて話す
(3)なるべく静かな場所で話す
(4)言い回しを変える(聞き取りやすい言葉を使う)
あなたはいくつ当てはまる?「聞こえの悪さ」チェック
下記の項目に当てはまる場合は、聞こえが悪くなっている可能性があるそうです。
(1)大勢での会話が聞き取りにくい
(2)高い音が聞こえにくい
(3)話し声が大きいと指摘される
(4)テレビの音量が大きくなりがち
<聞こえの状態を調べる「標準純音聴力検査」>
「標準純音聴力検査」は、耳の聞こえの状態を調べる基本的な検査。どのくらい小さな音まで聞こえるかを確認し、30dBを下回ると難聴と診断されます。30dBは、ささやき声が聞こえないレベルだそうです。
<誰でも簡単にできる!「オンライン聴覚検査」>
最近では聴覚検査がオンラインでも可能だそうです。例えば、東京医療センターの「オンライン聴覚検査」は、簡易的に聴覚検査を行うことができるサイト。誰でも簡単に行うことができるそうです。
聞こえの悪さの大きな原因 「加齢性難聴」

耳から入った音は鼓膜を振動させ、その振動が耳の奥にある渦巻状の「蝸牛」という器官に伝わります。蝸牛で振動が電気信号に変換され、脳で音として感じることができるのだとか。蝸牛の中には「有毛細胞」という細胞があり、微妙な音の振動を正確な電気信号に変換してくれています。しかし、年を重ねると有毛細胞が剥がれて減少。特に、高い音を担当する有毛細胞から減っていくので、加齢によって高い音から段々聞こえにくくなっていくそうです。先生によると、加齢性難聴のように少しずつ聞こえが悪くなる場合は、自分では気づきにくいとの事。そのため、60歳を超えたら2年に1回は聴力検査を受けるのがおすすめだそうです。
聞こえの悪さの落とし穴「リクルートメント現象」
リクルートメント現象とは、難聴者が音の変化を正常な人よりも敏感に感じてしまう現象。耳での音の調整が上手くいかず、小さな音は聞こえにくいのに、大きな音はうるさく感じたり不快に感じたりしてしまうそうです。
聞こえの悪さを引き起こす意外な原因
<意外な原因(1)「メタボ」>
動脈硬化を引き起こすといわれる「メタボリックシンドローム」。音を感じる蝸牛の血管はとても細いので、動脈硬化が起こると血流が悪くなり、有毛細胞の機能も低下しやすくなってしまうそうです。
<意外な原因(2)「ストレス」>
ストレスを感じると交感神経が働きます。すると、血管を縮めてしまい、有毛細胞への血流が悪くなることで、聞こえが悪くなってしまうそうです。
<意外な原因(3)「長時間のイヤホン」>
若い人でも聞こえが悪い人が増えているそうです。その原因がイヤホン。イヤホンを1日中つけて一定以上のボリュームで長い時間聞いていると、有毛細胞に負荷がかかり、難聴が早くきてしまうそうです。
難聴を治すことはできる?
内耳が悪くなる「感音難聴」は、1回悪くなると治すことができないそうです。視力が悪くなったらメガネをつけるように、歯が悪くなったら入れ歯を入れるように、聞こえが悪くなったら「補聴器」をつけることで生活の質を保つことができるそうです。(※治る可能性のある難聴もあるため詳しくは医師へご相談ください)
聞こえの悪さを放置しない!補聴器の最新事情
<(1)様々なデザイン>
補聴器の種類は大きく分けて3つ。デザインや色は様々で購入者の希望に沿って選ぶことができるそうです(※医療機関の受診なしでも補聴器は購入できます)。
(1)「耳穴型」目立ちにくさ:◎ 適応する難聴レベル:軽度〜中等度 価格:やや高め
(2)「耳掛け型」目立ちにくさ:◯ 適応する難聴レベル:軽度〜重度 価格:幅広い
(3)「ポケット型」目立ちにくさ:△ 適応する難聴レベル:中等度〜高度 価格:比較的安価
<(2)一人一人に合った音質>
聴力検査で聞こえにくかった音域を聞こえやすくするなど、一人一人の聞こえ方に合わせて補聴器を調整することができるそうです。さらに、最新の補聴器は人工知能も搭載されていて、人間の言葉とそれ以外を切り分けてくれるのだとか。そのため、BGMが流れているお店の中でも話し相手の声が聞き取りやすいそうです。
<(3)手厚い助成制度>
補聴器の価格は、片耳1台で約15〜20万円程度、両耳だと2台で30〜40万円程度。自治体によっては助成制度がない場合もあるそうですが、東京ではすべての区に助成制度があるのだとか。そのため、補聴器の購入を検討している場合は役所や補聴器専門店に一度確認してみると良いそうです。
<補聴器でヒアリングフレイルを予防しましょう>
先生によると、加齢性難聴の対処法は「補聴器」。補聴器で難聴の進行を止めることはできませんが、聞こえの悪さによって起こるコミュニケーションの障害や孤独感、認知機能の低下を予防することができるそうです。
(2025年8月24日(日)放送 CBCテレビ『健康カプセル!ゲンキの時間』より)
番組紹介
ニッポンの皆様に健康生活を!この言葉をキーワードにすぐに役立つ健康情報をお伝えします。「人」「家族」の未来を創り出す、CBCテレビの健康情報番組。