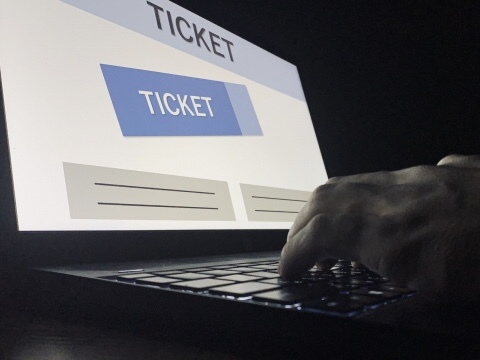伝統の相州だるまが可愛い馬に変身!平塚の干支だるま製作がピーク

今年も残すところ1か月あまり。全国各地で来年の干支「午(うま)」の置物作りが最盛期を迎えています。11月20日放送の『CBCラジオ #プラス!』では、神奈川県平塚市で江戸時代から続く「相州だるま」を使った干支だるまについて、荒井だるま屋4代目の荒井肇さんに話を伺いました。
関連リンク
この記事をradiko(ラジコ)で聴く赤いだるまが馬に変身
荒井だるま屋が製作する干支だるまは、高さ約12センチの伝統的な赤いだるまを土台に、耳や鼻などのパーツを紙粘土で形作り、全体に小さくちぎった和紙を貼って色付けします。
最後の工程では「深くご縁が結ばれますように」という願いを込めて、赤い紐を施します。こうした細かい作業の積み重ねで、かなり手がかかるそうです。
特徴的なのは、鼻先の青色です。荒井さんによると青の色は生命力や健康を願う縁起の良い色。魔除けや病気平癒などの意味が込められているそうです。
たてがみには金色のベースに金のラメを施しており、「縁起のように強いパワーの金色をなびかせて駆け上がる馬のイメージ」を表現しています。
江戸時代から続く相州だるまの歴史
相州だるまは、相模の国(神奈川県)のだるまで、江戸時代の幕末頃に群馬県から伝わりました。当時は現在の3倍ほどの大きさだった相模川を通じて、大きな船で運ばれてきたといいます。
荒井さんのこどもの頃には県内に10軒ほどのだるま屋がありましたが、現在では神奈川県内でわずか2軒になってしまいました。伝統を守り続けることの難しさがうかがえます。
干支だるまの製作は、2004年の申(さる)年から始まりました。再来年の未(ひつじ)年でちょうど干支だるまが丸2周、24年になります。
荒井さんが4代目を継ぐにあたり「自由にやらせてほしい」という思いから、様々な新作に挑戦した中のひとつが、この干支だるまだったといいます。
荒井さんは干支だるま以外にも、招き猫など「縁起のいいもの」を組み合わせた新作を次々と生み出しています。
「売れてますか?」という永岡歩アナの率直な問いかけに、「もう間に合わないです。ありがたいですね」と荒井さん。
年末から2月まで続く繁忙期
現在、製作は最も忙しい時期を迎えています。年末までがピークですが、その後も2月頃まで繁忙期が続くそうです。
干支だるまが一段落すると、今度は伝統の赤いだるまの販売や、会社名を入れた特注だるまの製作が佳境を迎えます。川崎大師の初売りや、2月まで続く「だるま市」もあるそうです。
「午」の干支だるまは1個4,500円。すべて手作りのため、ひとつひとつに温かみがあります。正面は可愛らしい馬の顔、背面には「八方除」の文字が書かれており、縁起物としても装飾品としても楽しめる作品です。
12年に一度訪れる干支のだるま。伝統工芸の技と現代デザインが融合した平塚の相州だるまは、新年を迎える縁起物として多くの人に親しまれています。
(minto)
番組紹介
読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。