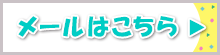2016年11月27日放送
教えて!ドクター
名古屋大学医学部附属病院 輸血部 教授 松下 正 先生)
★11月のテーマ「血液と健康」
<輸血不足問題について>
輸血に使われる血液は大きく分けて赤血球、血小板、それと凝固因子が含まれている新鮮凍結血漿の3種類があります。これらはすべて献血によって賄われます。ですので、皆さんが街の献血ルームや或いは街頭献血をしていただけないと、患者さんたちは大変困ってしまいます。今、この献血をされる方の人数が、大変減少しているというのが、大きな社会問題になりつつあります。特に若い20代の方の献血人数が過去15年ぐらいで半分になっているという、大変驚くべき統計があります。ただでさえ若い人の人数が減っているところへ、献血は何歳まででもできるわけではなく、65歳を過ぎていくと献血がだんだんできなくなります。そのため、若い人の献血人数が減るということは、将来何十年に渡って、輸血に使う血液の供給量がどんどん先細りになってしまうという、非常に怖い現実があります。一方で医療の進歩により、お年寄りの方も大きな手術ができるようになってきました。これまでできなかったような大きな手術にチャレンジされることが多くなってきました。そのために今まで助からなかった病気にかかっても、助かることが増えています。ただ、この手術による治療には、たくさんの輸血が必要なことがまだまだあります。そのため、そういった意味では医療の現場では、輸血血液の需要はむしろ以前よりも増加している傾向があります。これが今後、大変な問題になると思います。医療の現場からは、血液が患者さんの治療にとって必要であるということを、私たち輸血を担当する者がもっとアピールする必要があります。一方、厚生労働省や日本赤十字社も、もっと若者に語りかけて、献血に親しみやすくなってもらう、若者の考えや若者のマインドに合わせて、より献血に行きやすい雰囲気を作るとか、そういった努力が求められていると思います。若い人たちも誰かのために役に立つという意識が広まっていってくれるとよいです。本当に簡単なことでできますので、ぜひ若い方には一度、足を運んでいただきたいと思います。
スマイルリポート~地域の医療スタッフ探訪
<力を入れて取り組んでいる事>
がんセンター愛知病院の緩和ケアチーム、名称「地域がんサポートチーム」の専従看護師として活動しています。入院患者さんの痛みや吐き気、だるさ、不安などの苦痛症状について病院スタッフから相談を受け、チームで対応しています。また、退院して在宅療養されている患者さんの在宅医や訪問看護師と連携して、必要に応じて訪問診療をしています。今年5月から、地域がん診療連携拠点病院としての役割のひとつとしてがん患者の苦痛スクリーニングを「からだや気持ちのサポート問診票」というものを作成して行っています。必要な患者さんに早い段階から緩和ケアが提供されるように取り組んでおります。
<心に残っているエピソード>
現在は、「がん看護外来」という形で患者さん・ご家族の相談に対応していますが、以前は週に一度、病院玄関付近で机を準備して「がん看護相談」というものを開催していました。そこには、患者さん自身も相談にみえますが、付き添いで病院にみえたご家族が「抗がん剤を続けていけば、癌は消えるのですか。」とか「ここの病院では、手術は難しいと言われたのですが、他の病院に行けば手術してもらえるのですか。」とか、あと「抗がん剤で治療していくために、野菜の摂取や運動を患者さんに進めているのですが、行ってくれない。」「モチベーションを上げるためにはどうしたらいいですか。」または「抗がん剤治療をしているのですが、リンパ節に転移したと聞いたために、痩せている様子を見ると末期なのではないか、と思えてくるが、違うんですよね。」などと相談にみえていました。主治医の先生から病状を聞いて診察室では分かったつもりで返事をしていても、日常の様子を見ていると不安になり、どうすればよいかとご家族は悩まれると思います。
<現場で直面している課題>
そのようなご家族の手助けになるように「がんを学ぼう!家族カフェ」という愛知病院の地域緩和ケアセンターで家族が、がんの知識や日常生活のサポート、医療者とのコミュニケーション方法を学び、同じがん患者の家族との交流の中でお互いの悩みを分かち合い、将来のことを考える機会を持っていただければと思い、そういうものを開催しています。あと、「緩和ケア」というのは、診断された時から始まると言われていますが、まだまだ「緩和ケア」と聞くと最期のところで何をしてもらえるのか分からないという患者さんやご家族が多いです。誤解も多いです。当院では「緩和デイケア」という外来入院中のがん患者さん同士の交流を目的とした病気とともに生きることの支援も行っていますが、なかなか新規の利用者は少ないという現状があります。一度参加されると良かったと話されて、繰り返し来ていただけることも多いのですが、入りづらさを感じる方が多いように感じます。もっと気楽に地域緩和ケアセンターを利用してもらえるようになるといいなと思っています。